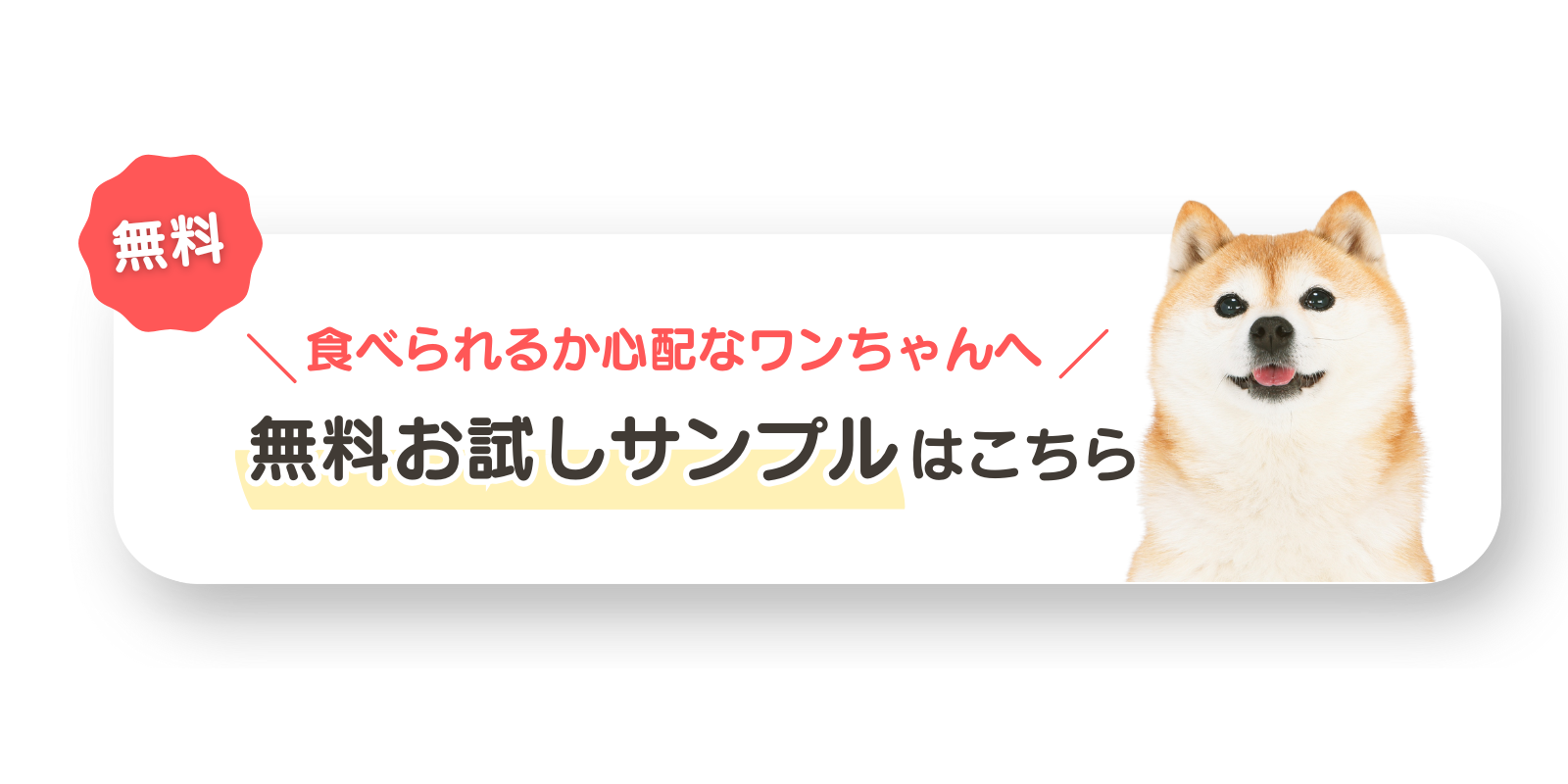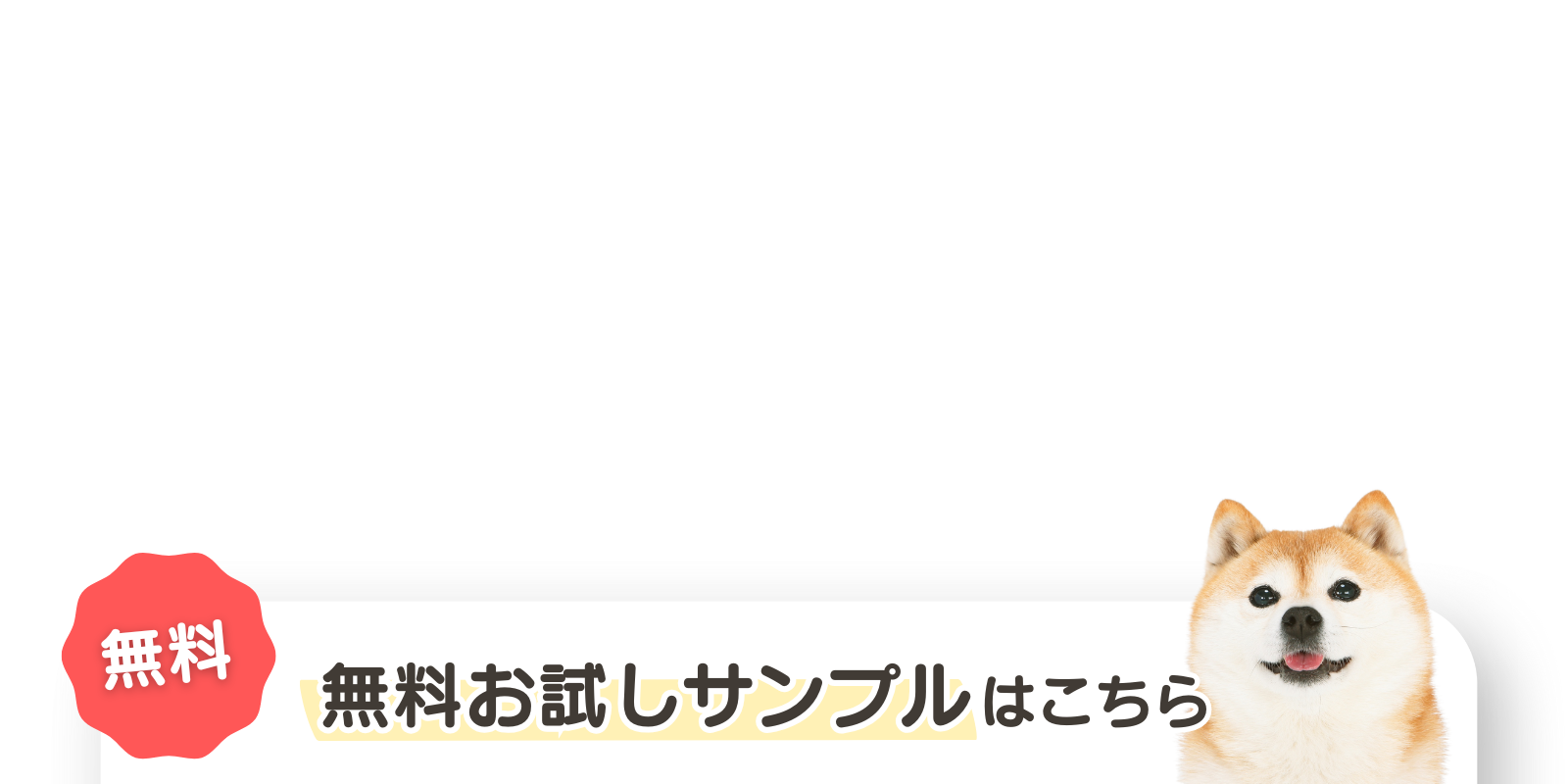老犬の夜鳴き・徘徊対策|認知症ケアの第一歩

「夜になると愛犬が落ち着かず鳴き続けてしまう」「部屋の中をぐるぐる歩き回って眠れない」──そんな夜鳴きや徘徊の行動に悩む飼い主さんは少なくありません。
特にシニア期に入った犬では、これらの行動が「認知症(犬の認知機能不全)」のサインであることもあります。
この記事では、老犬が夜鳴き・徘徊する原因、犬の認知症の理解、そして日常生活でできる工夫やケア方法について解説します。
| ■ 執筆者 トライザ株式会社 土田(動物看護師、トリマー) |
老犬が夜鳴き・徘徊する原因
シニア犬の夜鳴きや徘徊にはいくつかの要因があります。原因を正しく理解することが、効果的な対策の第一歩です。
1. 認知機能の低下(認知症)
最も多い原因のひとつが「犬の認知症」です。時間や場所の感覚がわからなくなり、昼夜が逆転して夜に落ち着かなくなります。
また、飼い主の存在や環境を認識できず、不安や混乱から夜鳴きを繰り返すこともあります。
2. 感覚器官の衰え
加齢により視力や聴力が低下すると、暗闇での不安感が増し、夜鳴きにつながります。見えにくさや聞こえにくさが犬にとって強いストレスになるのです。
3. 身体の不調や痛み
関節痛、心疾患、呼吸器のトラブルなど、体の痛みや不快感が眠りを妨げることがあります。シニア犬では複数の病気を抱えている場合も多く、夜間に不調が表れることがあります。
4. 環境ストレス
温度が合わない、寝床が不快、生活環境の変化なども夜鳴きの要因です。特に老犬は変化に敏感になりやすいため、安心できる環境づくりが重要です。
5. 飼い主さんとの依存・不安
高齢になると分離不安が強まり、飼い主さんがそばにいない夜間に鳴くケースもあります。
さまざまな原因がいくつか組み合わさっていることもあるため、判断が難しい場合は、動物病院で診察を受けることをおすすめします。
認知症(犬の認知機能不全)とは?症状と理解するポイント

犬の認知症は正式には「犬の認知機能不全症候群(Cognitive Dysfunction Syndrome:CDS)」と呼ばれ、老化によって脳の神経細胞が変化することで起こります。
主な症状(DISHAの5分類)
獣医分野では、犬の認知症症状を「DISHA」という頭文字で整理しています。
D(Disorientation:方向感覚の喪失)
同じ場所をぐるぐる歩き回る、壁にぶつかる、夜中に落ち着かなくなる
I(Interaction:交流の変化)
飼い主や家族との交流が減る、呼んでも反応が鈍い
S(Sleep-Wake cycle:睡眠リズムの変化)
昼夜逆転、夜鳴き、徘徊が増える
H(House-soiling:排泄の失敗)
トイレの場所がわからなくなる、粗相が増える
A(Activity:活動性の変化)
無目的に歩き回る、以前好きだった遊びに興味を示さない
同じような項目で、犬の認知機能・能力を評価し診断を裏付けるための基準「CCDR* 」というものもあります。
こちらの「認知機能評価テスト」は、愛犬がいま現在、認知症になっているのかのリスクをチェックができます⇩
3分程度でできるので、愛犬が認知症かも?と感じたらぜひやってみてくださいね。
飼い主さんに知ってほしいポイント

認知症は「しつけの失敗」ではなく、病気としてケアが必要な状態です。
「若い頃にはできていたのに…」
「どうしちゃったの?」
と、愛犬の変化をなかなか受け入れられない方も多いと思います。
ただ、ワンちゃん自身も戸惑ったり、不安に感じている場合が多いため、叱るのではなく「どう支えるか」を考えてあげてみてください。
予防や早期発見・早期対応で、症状の進行を緩やかにできる可能性があるため、できることから早めに取り組んでみましょう。
日常の工夫で改善する方法
夜鳴きや徘徊に完全な「即効薬」はありません。
しかし、生活習慣や環境を工夫することで、犬と飼い主の負担を大きく減らすことができます。
生活リズムの固定化
・日中の活動量を増やす:軽い散歩や知育トイを使って、昼間に体を動かす
・日光浴をさせる:太陽光を浴びることで体内時計をリセットしやすくなる
・食事時間を一定にする:規則正しい生活は睡眠リズムの安定に直結 など
昼間にしっかり活動させることで、夜はぐっすり眠れるようになり、夜鳴きや徘徊の改善につながります。
安心できる居場所づくり・環境整備
静かで暗すぎない場所にベッドを設置
真っ暗だと不安になる犬も多いため、常夜灯や足元ライトを活用
滑りにくい床にする
関節への負担を減らし、夜間の徘徊時の転倒を防止
サークルや柵で安全を確保
徘徊中に家具や壁にぶつからないよう、居住スペースを区切る
安心できる匂いを利用
飼い主さんの服やタオルを寝床に置くと、安心感につながる など
栄養面のケア(サプリメントを取り入れる)

近年、犬の認知症ケアには脳の健康を支える栄養素やサプリメントの重要性が注目されています。
DHA・EPA
脳神経の働きをサポートする代表的な成分で、多くのシニア用フードやサプリメントに含まれています。
抗酸化成分(ビタミンE・C、ポリフェノール)
ポリフェノールはたくさんの食品に含まれますが、特にサーチュイン遺伝子(長寿遺伝子)活性に関与する「グネチンC」(メリンジョ)という成分が注目されています。
中鎖脂肪酸(MCTオイル)
ブドウ糖に代わる、脳の「第2のエネルギー源」として利用できるという特徴があります。
バングレン(ジャワしょうが)
記憶力・学習力の維持に深く関わり、脳の神経幹細胞の分化・成長に欠かせない神経栄養因子様活性化合物のような働きがあり、人の認知症でも論文や多くの研究結果を残しています。
新しいアプローチとして注目されているため、DHA・EPAで効果を感じなかった、MCTオイルでお腹の調子が悪くなってしまった場合などはぜひ試してみましょう。
ペットフードだけで特定の栄養素を摂ろうとすると、含まれる食品をたくさん食べなくてはいけませんが、サプリメントなら効率的に摂取することができます。
「どのサプリメントを選んだらよいのか分からない」という飼い主さんは、動物病院に相談してみましょう。
動物病院で取り扱われている製品は、治療のサポートにも使われるなど研究結果がしっかりしたものが多く、安心して使用することができます。
動物病院と連携する大切さ
ちいさな疑問や違和感がある場合は、早めに動物病院に相談することがとても大切です。
・定期的な健康診断で、認知症以外の病気が隠れていないか確認できる
・獣医師による薬物療法や専門ケアを取り入れられる
・爪切りや耳掃除などのお手入れも一緒にお願いできる
・予防・早期発見・早期治療で健康な期間を延ばせる
夜鳴きや徘徊は飼い主さんにとって負担が大きくなりがちですが、「病院に相談する」という選択肢を持つことで安心感も得られます。
まとめ|老犬の夜鳴き・徘徊と向き合うために

・夜鳴き・徘徊の原因は、認知症、感覚の衰え、身体の不調、不安などさまざま
・犬の認知症は「病気」であり、叱るのではなくケアが必要
・生活リズムの固定化、環境整備、栄養面の工夫で改善が期待できる
・動物病院と連携することで、安心して愛犬をサポートできる
シニア犬の夜鳴きや徘徊は、飼い主さんにとっても辛く、眠れない日々が続くこともあるでしょう。
しかし、理解と工夫、そして適切なケアによって、愛犬の不安を和らげ、穏やかな時間を取り戻すことは可能です。
大切なのは「叱る」のではなく「支える」ことです。
ぜひ今日から、できることをひとつずつ取り入れてみてください。
\ 注目のジャワしょうが・メリンジョエキスが一緒に摂れる /
老化や脳ケアに役立つ病院専用サプリメント「トライザ」は、シニア犬の健康維持をサポートします。
全員もらえる!無料お試しサンプルは こちらから👇
執筆者:土田(トライザ株式会社 動物看護師、トリマー)