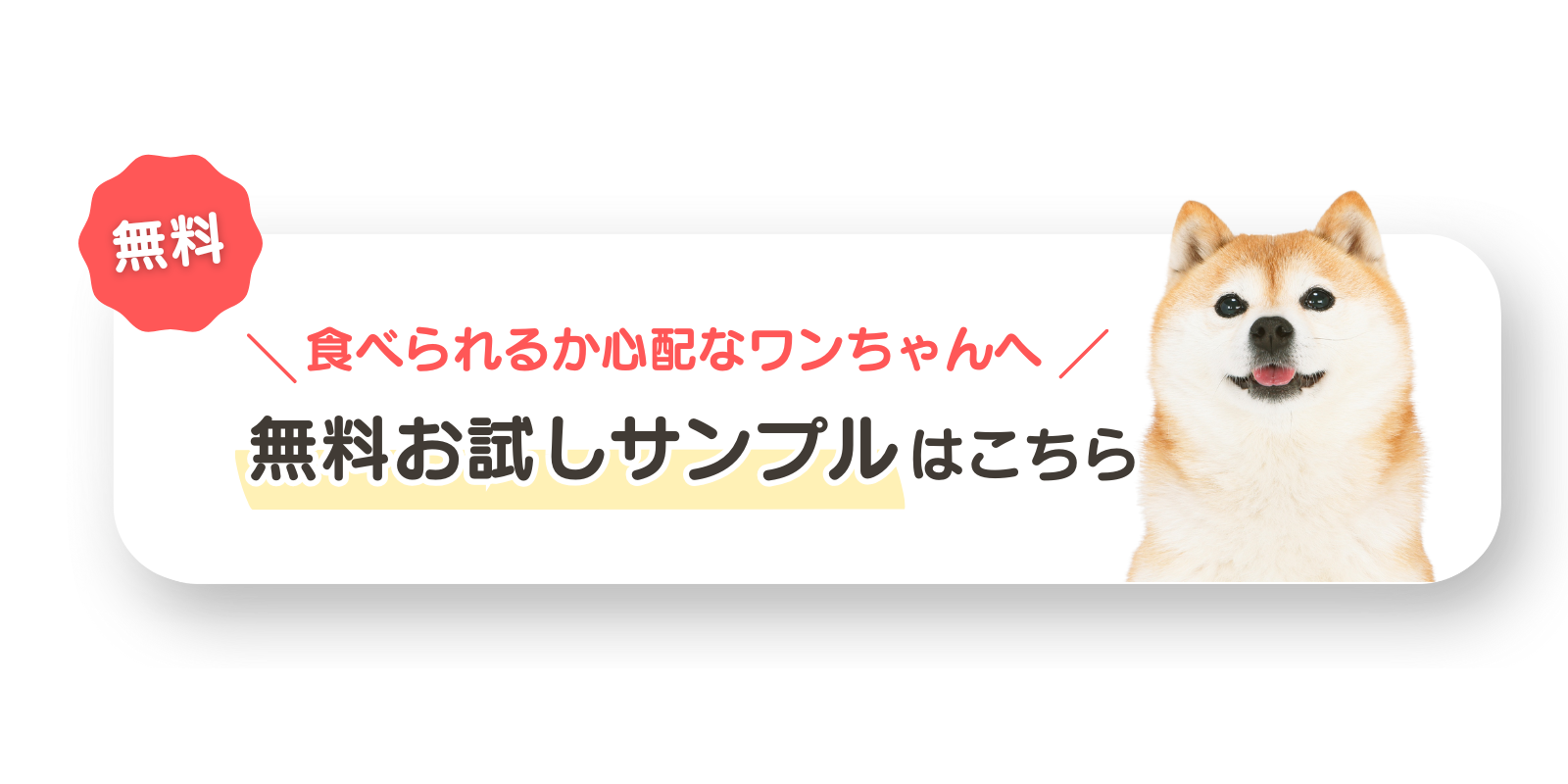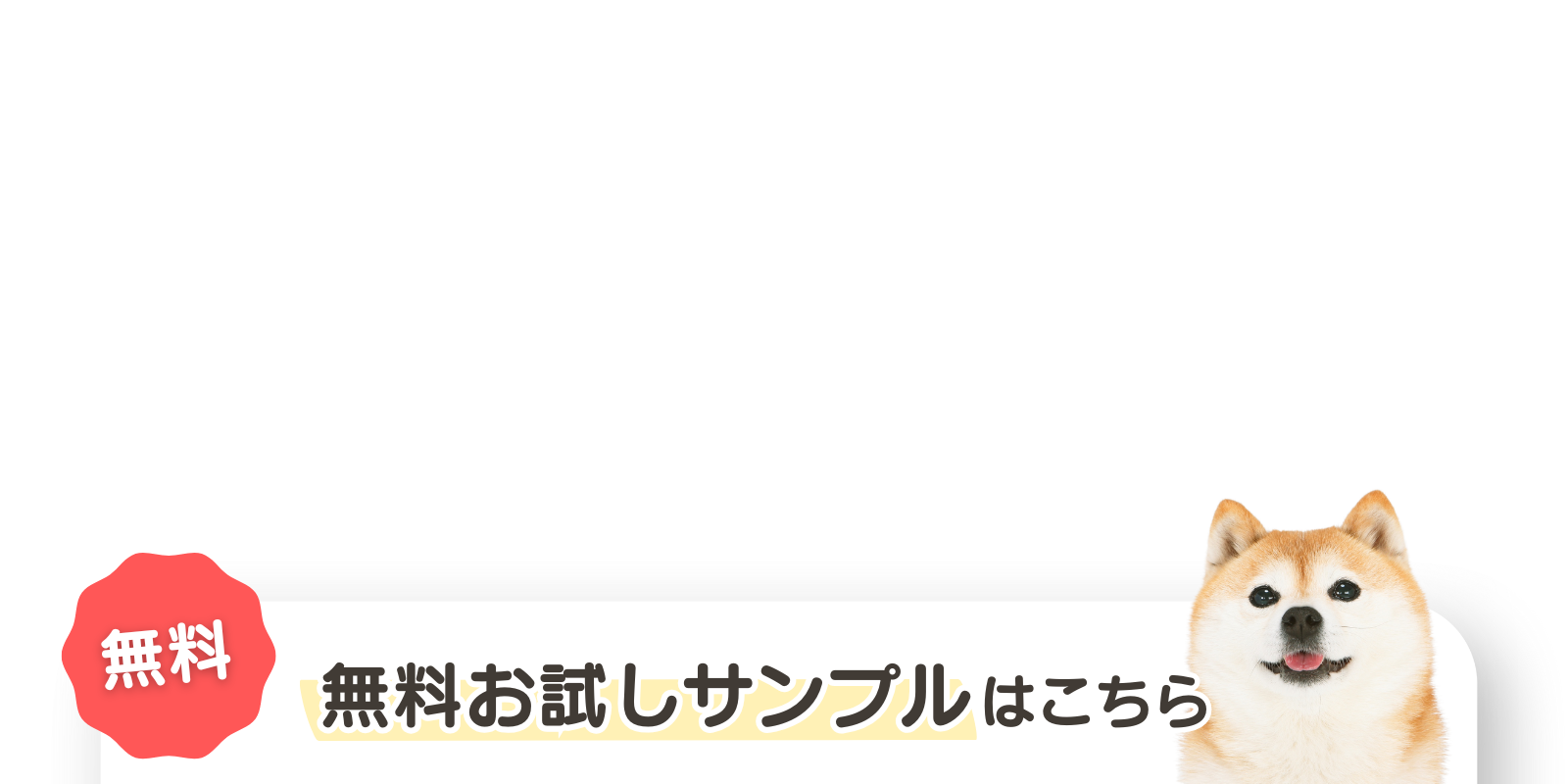動物介護士が解説|柴犬の夜鳴きに薬を使う前に!薬のリスクと対処法

「柴犬・日本犬は、認知症になりやすい」というイメージは、多くの柴犬の飼い主さんが持っているのではないでしょうか。
愛犬が夜鳴きをするようになったら、まず認知症を疑ってしまいますよね。
私自身、愛犬の夜鳴きの経験があるのでよくわかりますが、夜鳴きは近所迷惑の心配や飼い主さん自身の睡眠不足、愛犬の体力の心配、家族間の不和など、頭を悩ますこともたくさん起こってきます。
何とか夜鳴きを止めたいと、薬を使用することも検討しているのではないでしょうか。
そこで今回は、実際に愛犬に薬を使用したことがある動物介護士の私が、柴犬の夜鳴きに薬がおすすめできない理由や対処法を解説します。
柴犬の特性をふまえた夜鳴きの原因についてもご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
| 【執筆者保有資格】
動物介護士、ペットフーディスト、犬の管理栄養士 他 |
柴犬の夜鳴きの原因は認知症?違う理由の可能性もある
柴犬の夜鳴きをする理由は、主に以下の4つの原因が考えられます。
| ■ 柴犬の夜鳴きで考えられる原因
① 要求したいことがある |
そもそも、柴犬は“自分が興味がないことには反応しない”という性格の傾向があるため、無駄吠えをしにくい犬種です。
だからこそ、夜鳴きをするようになったら認知症なのかと心配になるのではないでしょうか。
しかし、夜鳴きにはさまざまな原因が考えられ、ただ薬を使用すれば良いというものではありません。
ここで、もう少し詳しく見ていきましょう。
① 要求したいことがある
本来、柴犬はあまり要求吠えをしない犬種です。
しかし、老犬になって身体の機能が衰え、思ったように体が動かせなくなることで、何かしてほしいことがある時に吠えるようになることもあります。
たとえば、お腹が空いた、散歩に行きたい、トイレに行きたいなど、何か訴えたいことがあるのかもしれません。
特に、老犬になればなるほど昼夜逆転しやすくなるため、夜になって吠える=夜鳴きとなるのです。
柴犬はとても賢く、飼い主さんを上手にコントロールするとも言われています。
自分の主張を通すために吠えている可能性もあるので、まずは要求吠えでないか確認しましょう。
犬の昼夜逆転については、以下の記事もチェックしてみてくださいね⇩
| 犬が昼夜逆転するのはなぜ?考えられる原因や治す方法を解説 |
② 痛みや不調がある
柴犬の夜鳴きの理由は、体のどこかに痛みを抱えていたり、違和感があるなどの不調によることも考えられます。
|
■ 柴犬がほかの犬種に比べてかかりやすい病気(※1) |
皮膚疾患はかゆみを伴うことが多く、緑内障では目に激しい痛みを伴うなど、我慢できない不調によって吠えているのかもしれません。
また、10歳以上の老犬の40%以上に背骨や関節の異常がみられるという報告もあります。
関節炎なやヘルニアなど、関節や神経の痛みを抱えている可能性も考えてあげる必要があります。
痛みや不調はストレスとなるのはもちろん、そのままにすれば病気を悪化させてしまうことにもなるため、柴犬が夜鳴きをするようになったらまずは獣医師にご相談ください。
③ ストレスを感じている
運動不足や食事量の不足など、ストレスを感じて夜鳴きをすることもあります。
特に柴犬が老犬の場合では、身体の機能の衰えから不安やストレスを感じやすくなるため、少しでもストレスを軽減できるように配慮してあげることが大切です。
寝床の環境は快適か、コミュニケーションの時間は十分かなど、見直してみると良いでしょう。
また、それまで飼い主さんに甘えることが少なかった柴犬でも、老犬になると様子が変わることがあります。
飼い主さんの姿が見えないことに不安となり、不安からストレスが溜まってしまうこともあるので注意してあげましょう。
④ 認知症を患っている
犬が長生きできるようになってきた一方、認知症にかかる犬の頭数も急増しています。
特に柴犬では、夜鳴きや夜に落ち着かない様子がみられると「あれ?認知症かも?」と思ってしまいますよね。
犬の認知症と夜鳴きの関係性ははっきりとわかっていませんが、不安感が一層強くなることも関係しているのかもしれません。
海外の研究によると、11〜12歳の老犬の28%、15〜16歳の老犬の68%に認知症の症状が現れたという報告もあります。(※2)
特に柴犬は認知症を発症しやすい犬種と言われているため、10歳を超えている場合は注意が必要です。
ただし、夜鳴きの原因はさまざまで、必ずしも認知症とは限りません。
飼い主さんが自己判断することはできないため、一度動物病院を受診することをおすすめします。
犬の認知症については、以下の記事をご覧ください⇩
| 動物介護士が解説|犬の認知症の症状は?予防や対策方法 |
|
動物介護士が解説|犬の認知症を治すことはできる?治療法やできるサポート |
柴犬の夜鳴きに薬を使ってもいい?薬は慎重に検討することが大前提

柴犬の夜鳴きの原因が認知症であった場合、薬を使用して夜鳴きを抑えたいという飼い主さんもいるでしょう。
特に夜鳴きで眠れない日々が続くと、藁にもすがる思いになりますよね。
しかし、内服薬が適さない場合や薬を使用することはリスクがあるため、獣医師と相談しながら慎重に検討することが大切です。
ここでは、柴犬の夜鳴きに処方される薬やリスクについて解説します。
認知症による夜鳴きに処方される薬の種類
残念ながら、夜鳴きを止める薬というものは存在しません。
そのため、対処療法として以下のような薬が処方されます。
| ■ 柴犬の夜鳴きに処方される薬の例
・睡眠導入剤 |
どの薬が処方されるかは、その柴犬の症状、持病、服用している薬などによって異なります。
実際、私の愛犬(柴犬ではありませんが)は丸1日寝ずに夜鳴きと徘徊をしていたため、体力を温存させる必要があると、神経遮断薬の一種であるアセプロマジンを処方されました。
獣医師が総合的に判断して薬を処方するので、愛犬の状態をまったく知らない動物病院ではなく、かかりつけの動物病院を受診することをおすすめします。
夜鳴きに薬を使用するリスク
夜鳴きに薬を処方されても、必ず効果があるとは限りません。
認知症の夜鳴きに処方される薬は「寝てもらうための薬」です。
薬には副作用のリスクがあるのはもちろん、長期的に柴犬の身体の負担となることもあります。
| ■ 夜鳴きに薬を使用するリスク
・薬に対する耐性が付いて効かなくなる |
私の愛犬はもともと心臓病があったため、「心臓に負担をかけるからできる限り飲ませないように」と指示されました。
処方された薬にどんなリスクがあるのか納得できるまで獣医師に確認し、慎重に扱うことが大切です。
柴犬の夜鳴きに薬を使用するときに注意すること3つ
夜鳴きに薬を使用することはリスクがあるため、獣医師も簡単には処方しないことがほとんどです。
ただ、柴犬の体力の消耗が懸念される場合、飼い主さんの精神的・体力的負担が大きい場合では、薬を処方してもらえることも多いでしょう。
慎重に扱う必要がある薬だからこそ、柴犬に飲ませるときは注意してあげなければいけないこともあります。
自分で通販などで購入して与えない
最近は、ネットで犬の薬を買うことができてしまいます
しかし、販売されている薬の成分や用量のわずかな違いが重大な副作用を引き起こしてしまうこともあり、とても危険です。
柴犬の夜鳴きに薬を検討する場合は、自己判断で薬を購入するのではなく、必ず獣医師の診察を受けましょう。
獣医師に指示された回数・用量を必ず守る
薬を処方されるときは、獣医師から飲ませるタイミングや飲んでいい量を指示されるため、必ず指示に従いましょう。
夜鳴きに処方される薬は、犬の負担や副作用を考えて最少の用量からスタートします。
効かないからといって過剰に摂取させてしまうと、命にかかわることもあるので注意が必要です。
「いつ飲ませるのか」「効かなかった場合はどれくらいまで与えていいのか」「いつ再投与の判断をするのか」をしっかり確認しておきましょう。
少しでも異変を感じたら服用を中止する
扱いに注意が必要な薬がおおいため、獣医師は最大限の注意を払って薬を処方しますが、少しでも異変を感じたら服用を止め、獣医師にご相談ください。
その際には…
✅ いつ飲ませたか
✅薬が効き始めるまでどれくらいの時間がかかったか
✅どれくらいの時間効果があったか
✅どんな異変があったか
を細かく伝えることで薬を変更するかの判断のサポートに役立ちます。
実際に愛犬も最少量で処方されたにもかかわらず、悲鳴のような声をあげながらそのまま倒れ、20時間眠り続けるということがありました。
最少量でも愛犬には多すぎたことが原因でしたが、明らかに異様な光景であることが想像できるのではないでしょうか。
薬は体質に合う・合わないがあり、柴犬によっては少ない量でも副作用が出ることがあるので、飲んだ後の様子もよく観察することが大切です。
柴犬の夜鳴きに薬以外の対処法も試してみよう

適切に使用していれば、薬を必要以上に怖がることはありませんが、薬を検討する前に薬以外の対処法も試してみましょう。
ちなみに、愛犬は薬を処方されていましたが、最初の数回だけでその後は薬に頼らず、対処法だけで穏やかに過ごすことができていましたよ。
もちろん、薬が必要なケースもあるので、その場合はできる限り薬の量を増やさずにいけるよう、対処法と併用することをおすすめします。
常に穏やかに接することを心掛ける
実は、柴犬の夜鳴きを助長させているのは飼い主さんということもあります。
夜鳴きが始まると、鳴き止んでほしくてつい強い口調で叱ってしまったり、イライラしてしまったりしていませんか?
叱ることでかまってもらえたと誤解され、ますます夜鳴きがひどくなることがあります。
また、犬は人に同調・共感する能力に長けており、一緒に暮らす期間が長いほど同期化することがわかっている(※3)ので、イライラした気持ちが伝わって夜鳴きを助長させてしまうことも考えられます。
夜鳴きをされると心に余裕がなくなって難しいかもしれませんが、愛犬に穏やかに接することを心掛けることも大切です。
日光浴をしてもらう
柴犬が昼夜逆転することで夜鳴きとなっていることもあるため、1日15〜30分程度の日光浴をさせてあげると良いでしょう。
日光浴には、体内時計のリセットや精神の安定、質の良い睡眠への誘導などさまざまな働きがあり、適度な日光浴は柴犬のからだ全体の健康維持に役立ちます。
また、メリハリのある生活を送らせてあげることを心掛け、日中は散歩に出たり一緒に遊ぶ時間を作るなど、「昼間は起きている」生活に誘導してあげましょう。
【関連記事】
| 動物介護士が解説|老犬が寝てばかりいるのは病気?注意点や気をつけてあげたいこと |
サプリメントを活用する
夜鳴きに効く薬がないように、夜鳴きを確実に止めるサプリメントは存在しませんが、脳に必要な栄養を補ってあげることは、穏やかな毎日に役立ちます。
認知症は十分な栄養が脳に行き届いてなかったり、体内の活性酸素が増えすぎてしまうことがひとつの要因と考えられているため、脳ケアに特化したサプリメントを活用しましょう。
認知症は進行する病気。
特に長寿傾向のある柴犬や日本犬は認知症になりやすいと言われているため、早い段階からサプリメントで効率よく脳に栄養を届けてあげましょう。
| ■ 脳ケアにおすすめの成分
・ポリフェノール(アントシアニン、グネチンCなど) |
脳ケアサプリメントの種類は豊富で、どれを選んだらいいか悩みますよね。
選ぶときは、動物病院でも取扱いのある、エビデンスのあるサプリメントがおすすめです。
実際に私が愛犬に与えて良かったと実感できたのは、動物病院でも販売されているバングレンとグネチンCが含まれたサプリメントでした。

もちろん、サプリメントも柴犬の体質に合う・合わないがありますが、合うものを見つけることができれば、健康的な認知機能へ導き、夜鳴きなどの悩みを解消したり和らげることに役立ってくれるでしょう。
まとめ

柴犬の夜鳴きに薬を使用したいと思うことは、悪いことではありません。
夜鳴きは体力を消耗させてしまうため、特に持病を抱えていたり体力の衰える老犬では薬も選択肢のひとつです。
しかし、薬にはリスクがあり、身体の負担となるのも事実。
できる限り負担を軽減してあげるためにも、薬だけに頼らず、対処法も合わせて実践してみてくださいね。
また、柴犬の夜鳴きはノイローゼになってしまう飼い主さんもいます。
おひとりで悩まず、獣医師や動物看護師、動物介護士などの専門家に相談して解決法をみつけてください。
愛犬との限られた時間を、穏やかに、幸せにすごせますように。
\バングレン・グネチンC配合/
老化や脳ケア、シニア犬のからだ全体の健康維持に役立つ動物病院専用サプリメント「トライザ」の無料お試しサンプルは ↓ から
執筆者:高田(動物介護士)