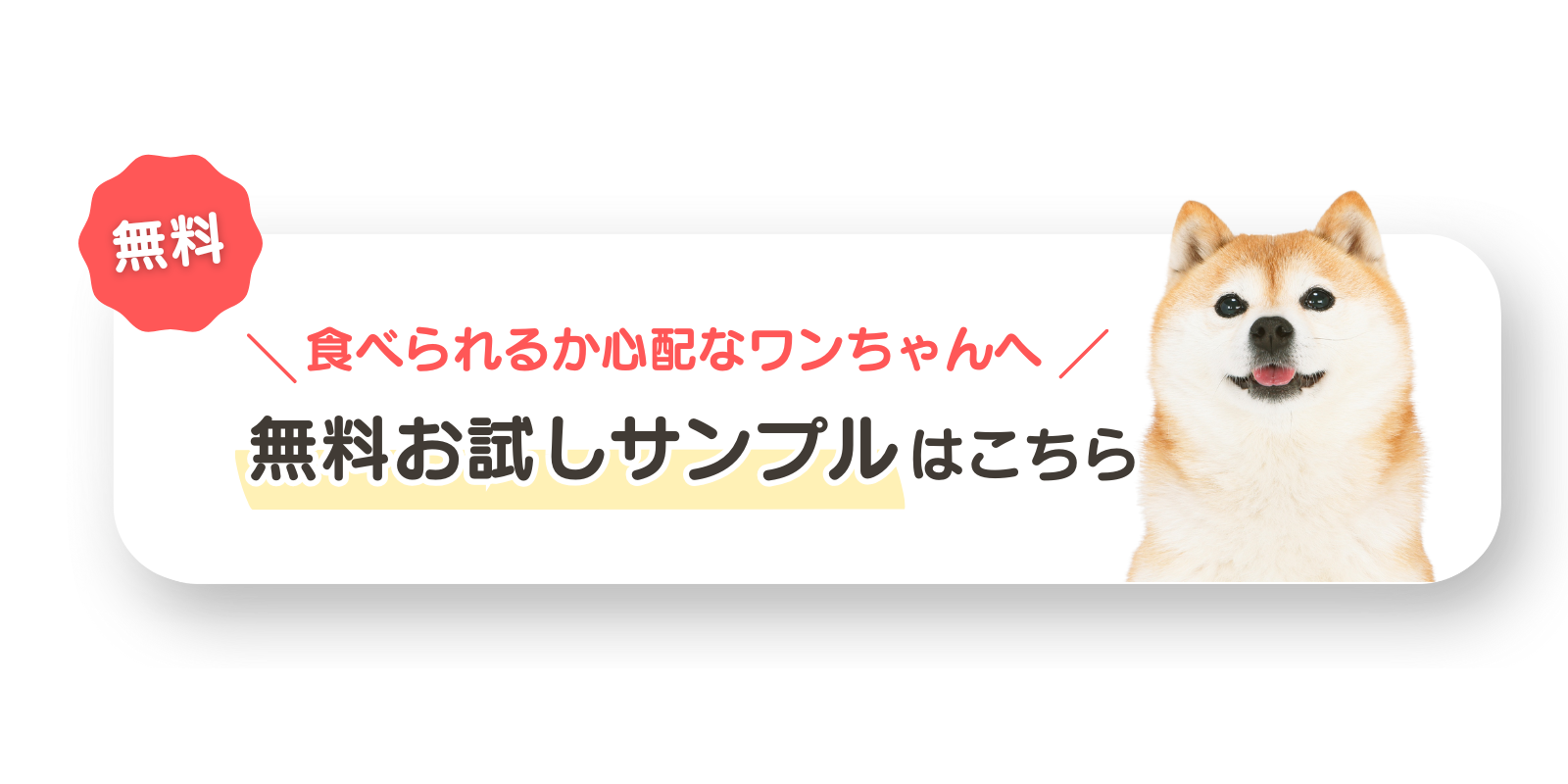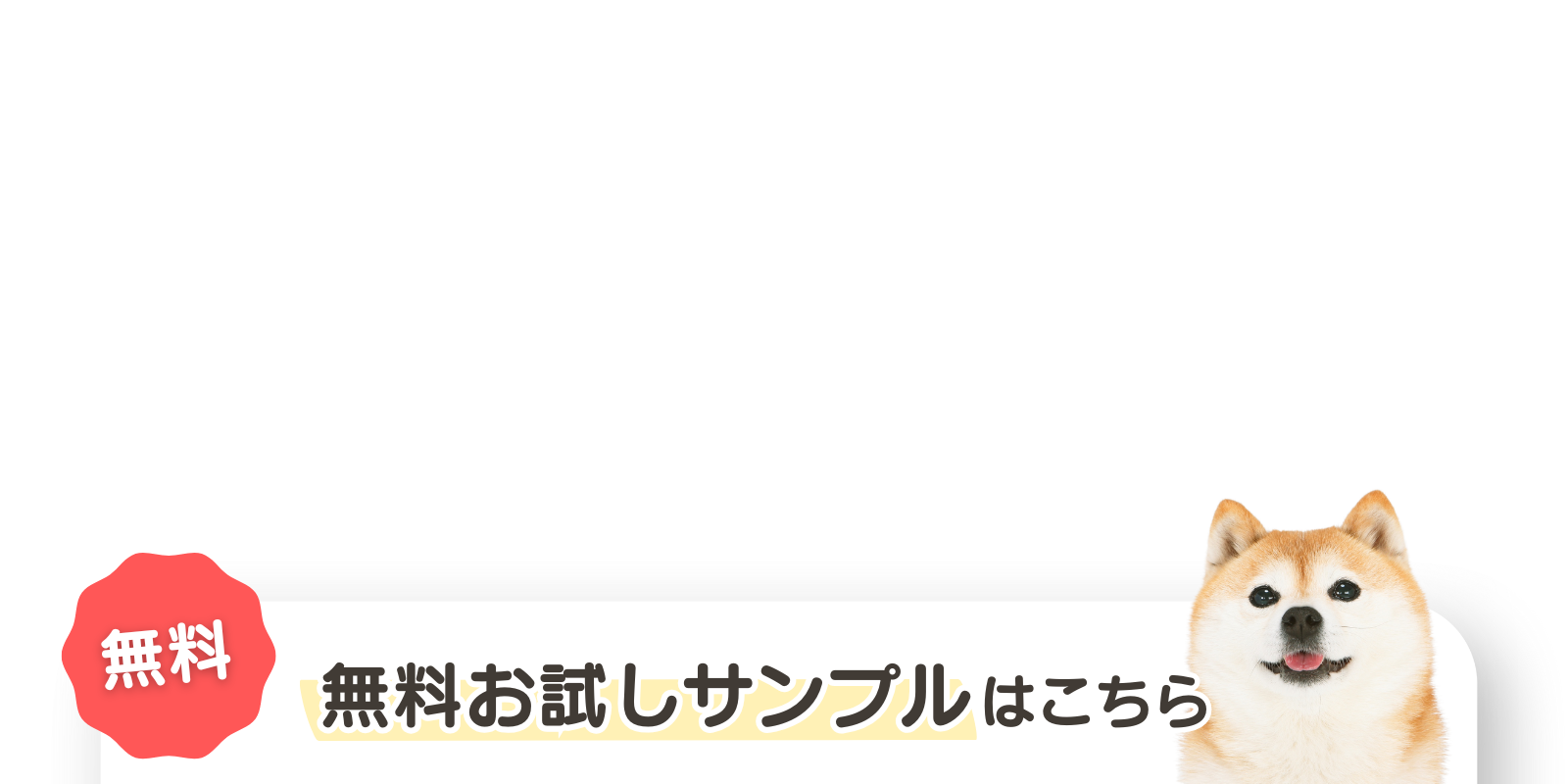動物介護士が解説|犬の認知症の症状は?予防や対策方法

犬もシニアになると老化に伴いさまざまな身体の機能が衰え、認知症を発症することもあります。
認知症は進行する病気ですが、今のところ治療薬はなく完治させることはできません。
犬の認知症は10歳を過ぎた頃から始まり、11〜12歳の犬の28%、15〜16歳の犬の68%に症状がみられるという報告もある(※1)ため、早めの対処が重要です。
そこで今回は、動物介護士の資格を持ち実際に認知症の愛犬と暮らしていた私が、犬の認知症の症状や予防法、認知症の進行を抑える対策法を解説します。
「もしかして愛犬は認知症?」「何かできることはある?」と悩んでいる飼い主さんはぜひ参考にしてください。
|
■ 保有資格 動物介護士 / ペットフード安全管理者 / ペットフーディスト 他 |
犬の認知症の症状・特徴は?認知症は早期発見が鍵
犬の認知症の症状は、分かりにくいものから明らかに異常だと分かるものまでさまざまです。
| ■ 犬の認知症の主な症状 ・トイレの失敗が増えた ・できていたことができなくなった ・昼夜逆転 ・夜鳴き ・抑揚のない声で吠え続ける ・徘徊(うろうろ歩き回る)や旋回運動(クルクル回る)がみられる ・反応が鈍い、無反応 ・家の中で迷う ・狭いところに入って出てこれない ・性格の変化 など |
通常、徐々にこうした症状がみられるようになり、症状は犬によっても異なります。
しかし高齢犬の場合では、何らかの病気から回復した後や入院後などに急に症状がみられるようになることもあり、注意が必要です。
実際、愛犬は重度の大腸炎で1週間ほど入院し、退院してきてから急に認知症の症状が現れました。
認知症は早期発見が鍵となるため、認知症の症状の特徴を覚えておきましょう。
特徴①自分の居場所や周囲の環境が把握できない
犬も認知症になると、自分の居場所や周囲の環境が把握できなくなってきます。
具体的な症状は以下のとおりです。
- 床や壁をぼーっと見つめる
- 目的もなくウロウロと歩き回る(徘徊)
- 壁やドアにぶつかる
- こぼした食べ物が見つけられない
- 飼い主さんが分からなくなる
- 知っている人や動物が分からない
- 狭いところに入りたがる
- 壁の前で立ち尽くしたまま動かない など
最初は、床や壁をぼーっと見つめる、こぼした食べ物を見つけられない、狭いところに入りたがるなどの何気ない行動ですが、認知症が進行すると飼い主さんのことも分からなくなってしまいます。
老犬の徘徊については以下の記事で詳しく解説しています。
| 動物介護士が解説|老犬が徘徊する理由は?考えられる原因や対策法 |
特徴②人やほかの動物への接し方が変化する
認知症になった犬は、人やほかの動物への接し方も変化してきます。
具体的な症状は以下のとおりです。
- 飼い主さんの帰宅時に迎えに行かない
- 飼い主さんの帰宅を喜ばない
- 撫でられたり褒められたりしても喜ばない
- 反応が鈍くなる
- 性格に変化が見られる
- 飼い主さんにも反応しなくなる など
認知症になると反応が悪くなりがちですが、最初はなんとなく反応が鈍いと感じる程度です。
認知症の進行に伴い、あらゆる反応がなくなっていきます。
特徴③昼夜逆転など睡眠時間が変化する
認知症は視交叉上核(しこうさじょうかく)という神経細胞の働きが低下する傾向があり、体内時計が狂いやすくなります。
そのため、以下のような症状がみられるようになります。
- 昼間に寝て夜に起きている
- なかなか寝ない
- 眠りが浅くすぐに起きる
- 長時間寝ている
- 夜間に徘徊する
- 夜鳴きをする など
老犬になると若い頃よりも睡眠時間が長くなるのは自然なことなので、最初は気づきにくいでしょう。
しかし、徐々に夜間の徘徊や夜鳴きなどが増え、飼い主さんが制止できない状態になります。
老犬の夜鳴きや夜に寝ない場合の対処法については以下の記事を参考にしてみてください。
| 動物介護士が解説|老犬の夜鳴きに薬は効く?使用するリスクや対処法 |
| 動物介護士が解説|老犬が夜寝ないけど大丈夫?原因と対処法 |
特徴④トイレの失敗が増える
それまでちゃんとトイレで排泄できていたのに、失敗が増えるようになったときも認知症の発症が疑われます。
具体的な症状は以下のとおりです。
- トイレ以外の場所で排泄することが増える
- 排泄前のウロウロやグルグルなどの前兆がなくなる
- トイレの場所が分からなくなる
- お漏らしするようになる など
このほか、「お手」や「おすわり」などのコマンドも分からなくなります。
特徴⑤普段の行動が変化する
認知症になると、普段の行動にも変化がみられるようになります。
具体的な症状は以下のとおりです。
- 落ち着きがなくなる
- 寝てばかりいる
- 無関心になる
- 無気力になる
- 無駄吠えが増える
- 目的なくウロウロと歩き回る(徘徊)
- 円を描くように回り続ける(旋回運動)など
最初は落ち着きがなくなって、ソワソワしていたり寝てばかりいるような程度ですが、認知症が進行すると徘徊や旋回運動(ぐるぐる回る)が見られるようになります。
また、私の愛犬では無表情、尻尾を振らなくなったという症状もありました。
認知症の症状は少しずつ現れるケースが多いため、老化と決めつけずに見逃さないことが大切です。
老犬が寝てばかりいるときの注意点については、以下の記事をご覧ください。
| 動物介護士が解説|老犬が寝てばかりいるのは病気?注意点や気をつけてあげたいこと |
注意!認知症に似た症状が出る病気

トイレの失敗をする
犬がトイレを失敗するときに考えられる主な病気は以下のとおりです。
| ■ 犬のトイレの失敗で考えられる主な病気 膀胱炎 / 尿石症 / 尿路系腫瘍/ 副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)/ 糖尿病 / 腎臓病 / ホルモン疾患 / 前立腺肥大 など |
ほかにも、避妊手術をしたケースでは、年を取ってから尿漏れが起こるようになる、足腰が痛くてトイレまで行けないなど、病気以外にも考えられる要因があります。
夜鳴きや徘徊をする
実は夜鳴きや徘徊といった症状は、認知症ではなく病気が原因となって起こる可能性があります。
犬の夜鳴きや徘徊で考えられる主な病気は以下のとおりです。
| ■ 犬の夜鳴きや徘徊で考えられる主な病気 脳炎 / 脳腫瘍 / 前庭疾患 / 神経疾患 / 甲状腺機能低下症 / 副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)/ 腎臓病 / 糖尿病 など |
また、体のどこかに痛みを抱えている場合でも夜鳴きをしたり、痛みや息苦しさから徘徊することもあります。
老犬の夜鳴きについては、以下の記事も参考にしてみてくださいね。
| 動物介護士が解説|老犬の夜鳴きに薬は効く?使用するリスクや対処法 |
指示がとおらない・反応が鈍い
これまでの指示がとおらなかったり、反応が鈍いなどの場合は、視覚・嗅覚・聴覚などが衰えているのかもしれません。
加齢による自然なものであれば問題はありませんが、目の疾患などが隠れている場合もあるため動物病院にご相談ください。
性格の変化
性格の変化や急に攻撃性がみられるようになったときも、認知症だけでなく病気を疑う必要があります。
| ■ 犬が急に攻撃的になったときに考えられる病気 脳炎 / 脳腫瘍 / 水頭症 / 甲状腺機能低下症 など |
もちろん、老化に伴い不安やストレスを感じやすくなったり、体の痛みから触られたくない、視覚や聴覚の衰えで急に触られてびっくりするなどといったことも考えられます。
認知症になりやすい犬は?10歳以上の犬は注意!
冒頭でも触れましたが、すべての犬が認知症になる可能性があります。
1歳年を重ねるごとに認知症のリスクが52%増えるという報告(※2)もあるなど、高齢になるほど認知症になりやすいと言えるでしょう。
諸説ありますが、そのなかでも特に注意したいケースがあります。
|
■ 特に認知症になりやすいといわれている犬の特徴 |
このほか、避妊手術の有無や性別の違い、体の大きさによる違いなどもさまざまな報告がありますが、報告によって結果が異なるため明確にはなっていません。
いずれにしても、どの犬も認知症になるリスクはあるので、早めに対処することが大切です。
認知症の原因
犬の認知症で最も多いのは、脳の神経細胞が破壊されてしまうことで起こるアルツハイマー型認知症です。
|
■ 犬の認知症発症の主な原因 脳の神経細胞が破壊されて減少する 神経伝達物質の減少 脳で生成されるタンパク質の1種「アミロイドβ」が排出されずに蓄積する |
脳の神経細胞が破壊されてしまう原因は、老化によって脳細胞に栄養がきちんと行き渡らなくなったり活性酸素による酸化ストレスなどが主と考えられています。
活性酸素はアミロイドβにも影響を与え(※5)、アミロイドβが蓄積するほど活性酸素の発生量が増えるという悪循環に陥ってしまうのです。
では、犬の認知症を予防するためにはどうしたらいいのでしょうか。
次章から予防法や対策方法について解説します。
犬の認知症の予防や対策法6つ
犬の認知症は脳の老齢性変化であり、完全に予防することはできません。
しかし発症を遅らせたり、進行を抑えることは可能です。
|
■ 犬の認知症の予防・対策法6つ ・定期的に動物病院を受診する ・脳に適切な刺激を与える ・日光浴を兼ねた散歩をする ・多様性のある食事にする ・最適な栄養(フード、サプリメント等)を取り入れる ・いつも通りに接する など |
実際、私は高齢愛犬4匹に早い段階から対策を行っていたので、17歳を過ぎるまで認知症の症状がみられることはありませんでした。
また、症状が現れても対策法を組み合わせることで進行を抑えることができていたので、ぜひ実践してみることをおすすめします。
①定期的に動物病院を受診する
愛犬に認知症の症状がある・ないに関係なく、シニア期に入ったら定期的に動物病院を受診しましょう。
| ■犬の一般的なシニア期の目安 ・小型犬…7歳頃~ ・中型犬…7歳頃~ ・大型犬…5歳頃~ |
犬がシニア期に入ると、体のさまざまな機能が衰えはじめます。
病気にもなりやすくなるため、定期的な健康診断で病気の早期発見・早期治療をすることがとても重要です。
また信頼できるかかりつけの動物病院を見つけておくことで、愛犬が認知症になったり、不調を起こしたときも相談しやすくなります。
②脳に適度な刺激を与える
認知症の進行を早める原因のひとつに、脳への刺激不足があります。
刺激が少ないと脳細胞が減少してしまうため、脳細胞を活性化させるためにも適度な刺激を与えてあげることが大切です。
|
■ 犬の脳を刺激する方法 ・ノーズワーク(嗅覚を使って食べ物を探すゲーム) ・ドッグランなどでほかの犬との交流 ・引っ張りっこ ・かくれんぼ ・ボール遊び ・散歩コースの変更 など |
私は愛犬たちに毎朝ノーズワークマットを使って、おやつ探しをしてもらっていました。
ノーズワークはあまり活発に動けない犬でも室内でできるので、取り入れやすいでしょう。
③日光浴を兼ねた散歩をする
運動不足の犬は認知症になりやすいとされているので、日光浴を兼ねて散歩に連れて行ってあげましょう。
散歩で普段と違った景色や匂い、音、温度など、さまざまな刺激を脳に与えてくれます。
また、日光を浴びることで脳内伝達物質のひとつであるセロトニンの分泌が促され、ストレスの軽減や体内時計の調整、質の良い睡眠への誘導など嬉しい作用もあります。
さらに、日光によって体内でビタミンDが生成されますが、ビタミンDは認知機能とも大きく関係があり、ビタミンDが不足するとアルツハイマー型認知症の発症リスクが上がるという報告もあるので日光浴も重要しょう。(※6)
自力で歩けない犬や高齢犬などは、介助ハーネスや抱っこ、ペットカートなどを利用して散歩に連れ出してあげることをおすすめします。
④多様性のある食事にする
愛犬の食事内容をひとつのものに決めるのではなく、朝、昼、夜のフードローテーションをしたり、トッピングのバリエーションを増やすなど、多様性のある食事にしましょう。
人間での研究報告では、さまざまなものをバランスよく食べた場合、認知機能が低下しにくいという結果になっています。(※7)
犬での研究は行われていませんが、同じドッグフードばかり食べているとほかの栄養素を摂り入れることができないため、さまざまな栄養素を摂り入れるという点でもメリットはあるでしょう。
ドッグフードの主原料である動物性タンパク質の種類を変えたり、野菜や果物をトッピングするなどの方法が手軽にできておすすめです。
老犬のドッグフードの選び方については、以下の記事を参考にしてみてください。
| 専門家が解説|老犬のドッグフードの選び方は?押さえておきたいポイント6つ |
⑤最適な栄養(フード、サプリメント等)を取り入れる
シニア期に関わらず、基本的な栄養素をきちんと摂取できていることが大切です。
基本的な栄養素の接種に加えて、体調面や年齢、犬種などの条件で必要な栄養素をサプリメントなどで補給しましょう。
活性酸素は体内でさまざまな役割を担う重要なもので、体内には酸化から体を守る防御機能がありますが、活性酸素と防御機能のバランスが崩れることで体にさまざまな悪影響を与えます。
加齢によって防御機能が衰え、活性酸素が増えすぎてしまうことから酸化から体を守る成分が配合されたサプリメントでサポートすることがおすすめです。
| ■ 酸化から体を守る成分 ・ポリフェノール(アントシアニン、グネチンCなど) ・カロテノイド(アスタキサンチン、ルテイン、β‐カロテンなど) ・DHA ・ビタミンA、C、E など |
上記のなかでは、強力な抗酸化作用をもつグネチンCという成分をおすすめします。
また、脳細胞の健康維持に脳の神経幹細胞に働きかけて神経細胞の新生(分化)を促すバングレンという成分は、新規細胞の成長や維持に深く関与すると考えられている神経栄養因子のような働きをすることがさまざまな試験から明らかになっています。
実際、認知症になった愛犬にグネチンCとバングレンが配合されたサプリメントを継続して与えていたら、体質に合っていたようで良い状態で維持できていました。
愛犬の体質にあったサプリメントを見つけることができれば、健康的な脳機能へ導いてくれるでしょう。
なお、サプリメントにはさまざまなものが販売されていますが、成分含有量が僅かなものもあるため、動物病院で販売されている製品がおすすめです。
⑥いつも通りに接する
愛犬が認知症であった場合も、声掛けしたり一緒に遊んだり、スキンシップを取るなどいつも通りに接してあげることが認知症の進行を抑えることにも役立ちます。
認知症は進行する病気ですが、進行を早める要因には刺激不足やストレスなどが挙げられます。
認知症になると「そっとしておいたほうがいいのではないか」「話しかけても分からないし…」と思うこともあるかもしれません。
しかし、犬にとって飼い主さんとのコミュニケーションはとても重要で、コミュニケーションが刺激やストレス軽減になるため、いつも通りに接してあげましょう。
まとめ

症状を見逃さず、早期発見してしっかり対処することで進行を緩やかにすることも可能です。
|
■ 犬の認知症の主な症状 |
愛犬が認知症になることを受け入れがたいことがあるかもしれません。
しかし、認知症もひとつの個性であり、上手に付き合っていくことができる病気です。
おひとりで悩まず、動物病院の獣医師や動物看護師に相談しながら愛犬が快適に過ごせるようにサポートしてあげましょう。
老化や脳ケア、シニア犬のからだ全体の健康維持に役立つ動物病院専用サプリメント「トライザ」の無料お試しサンプルは ↓ から

<参考文献>
※1:National Library of Medicine「Prevalence of behavioral changes associated with age-related cognitive impairment in dogs」
※2:scientific reports「Evaluation of cognitive function in the Dog Aging Project: associations with baseline canine characteristics」
※3:petMD「Dog Dementia: Symptoms, Causes, Treatment and Life Expectancy」
※4:動物臨床医学「犬と猫の高齢性認知機能不全」
※5:日本ヒューマンケア科学会誌「「生活習慣病・活性酸素・栄養」シリーズ(1)」
※6:日本老年医学会雑誌「二次予防事業対象者の認知機能とビタミンD」
※7:国立長寿医療研究センター「食事と認知機能(4)【認知症予防】」
執筆者:高田(動物介護士)