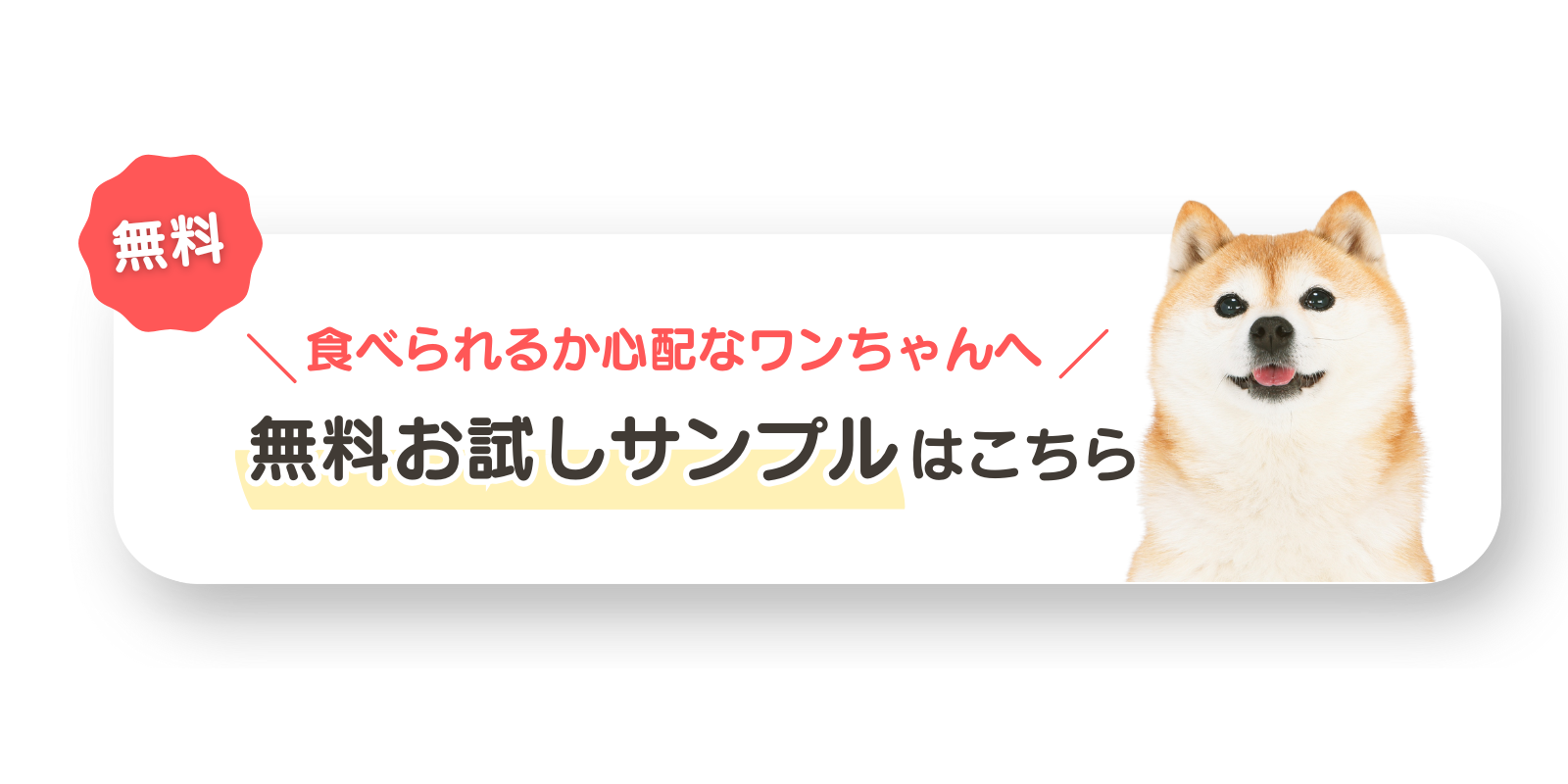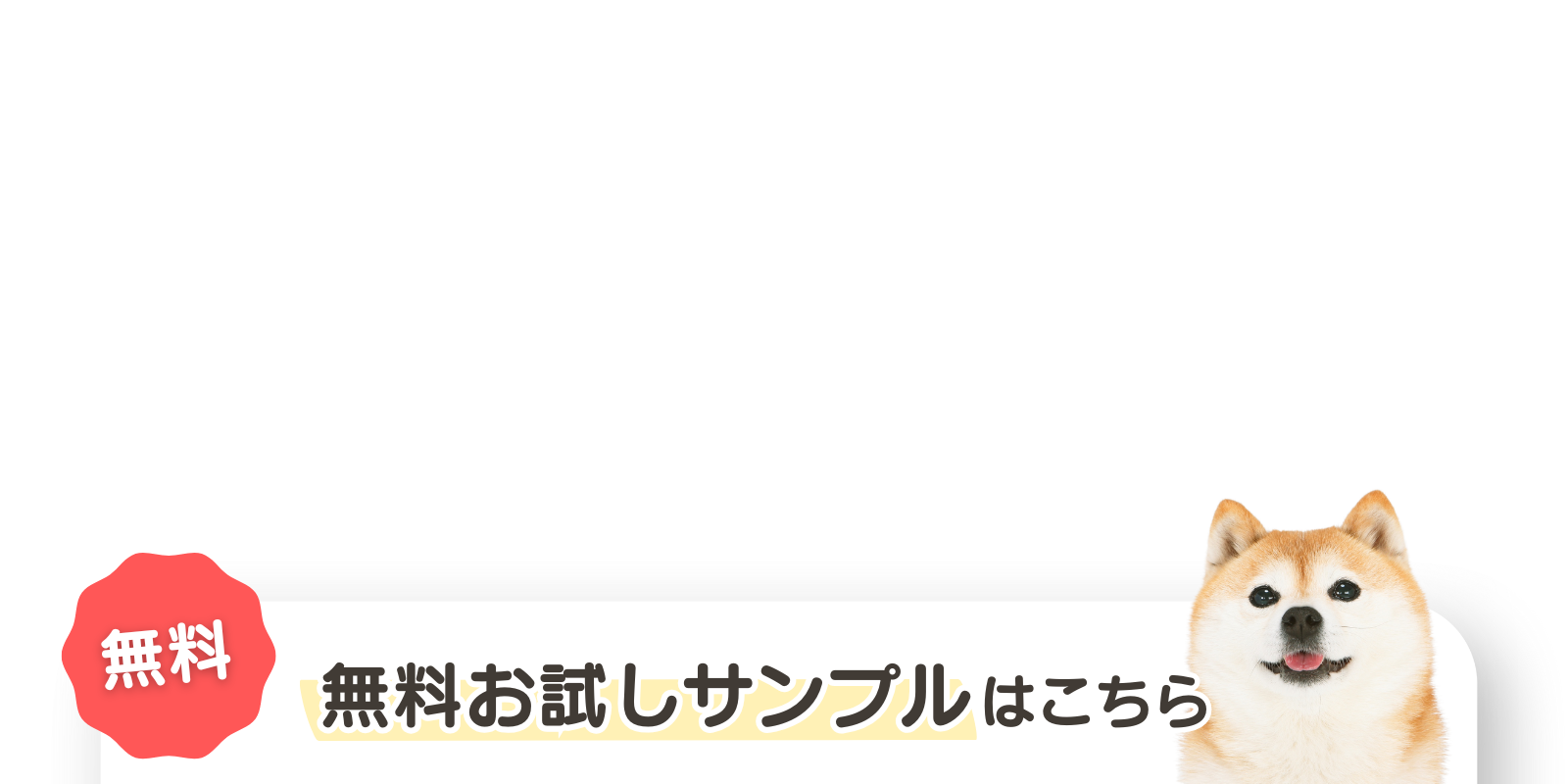動物介護士解説|老犬のワクチン接種はいつまで必要?注意点や負担を減らす方法

愛犬が老犬になると疑問に思うのが、毎年行っていたワクチン接種はいつまで行うのだろうということではないでしょうか。
「老犬にワクチン接種は必要なのか」、「体に負担となるのではないか」と心配になることもありますよね。
今回は、そんな老犬のワクチン接種について、実際に高齢の愛犬たちと暮らしていた動物介護士の私が解説します。
ワクチン接種の負担を減らす方法や注意点も紹介しているので、ぜひ参考にしてくださいね。
| 【執筆者保有資格】
動物介護士、ペットフーディスト、犬の管理栄養士 他 |
そもそもワクチン接種とは?狂犬病ワクチンと混合ワクチンの2つ

犬のワクチン接種には、法律上の義務である「狂犬病ワクチン」と任意で行う「混合ワクチン」があります。
混合ワクチンは接種を推奨されているものの、法律的に義務づけられているわけではないため、“絶対に接種しなければいけないもの”というわけではありません。
しかし、トリミングサロンやドッグラン、犬同伴可能な施設などでは狂犬病ワクチンの接種証明書と混合ワクチンの証明書の2つを求められます。
そのため、2つのワクチン接種を行うのが一般的でしょう。
では、なぜワクチン接種が必要なのでしょうか。
最初に、ワクチン接種の必要性や副作用、ワクチン接種をしないリスクを見ていきましょう。
狂犬病ワクチン接種の必要性
狂犬病は、発症すると治療法がないことから致死率はほぼ100%の人獣共通感染症です。
日本での狂犬病は、1957年(昭和32年)の動物での発生を最後に国内での発生はなく、日本は狂犬病清浄国のひとつですが、狂犬病清浄国は世界に数地域しかありません。
また、狂犬病はすべての哺乳類に感染しますが、日本に輸入される動物で狂犬病の検疫対象となっているのは、犬・猫・あらいぐま・きつね・スカンクのみです。
人気のフェレットやうさぎなど、もし狂犬病ウイルスを保有していても気づかれることなく日本に入国できてしまいます。
このように、日本で狂犬病の発生はないとはいえ、いつ海外から持ち込まれても不思議はありません。
そのため、日本では飼い犬の狂犬病ワクチンの接種を飼い主に義務づけています。
しかし、日本のように狂犬病ワクチンを義務付けている国はわずかで、オーストラリアは狂犬病が発生したことが分からないという理由から禁止、イギリスは任意です。
その代わり、狂犬病になってしまったときは発症の有無にかかわらず処分されます。
愛犬を狂犬病から守るとともに、愛犬を発生源にしないためにも狂犬病ワクチン接種は必要なのです。
混合ワクチン接種の必要性
混合ワクチンは、致死率が高い感染症を予防するためのコアワクチンと、地域の感染状況やライフスタイルによって感染リスクがある場合に接種するノンコアワクチンがあります。
| 【コアワクチン】
すべての犬に接種が勧告されているもの 【ノンコアワクチン】 |
これらの感染症は治療法がなく、命を落とすこともあります。
特に子犬や老犬では注意が必要で、ワクチンを接種しておくことで感染しても発症しなかったり、発症しても重症化しにくい、感染を広げないなどに有効です。
私は実際に、持病でワクチン接種ができない高齢の愛犬が、新しくお迎えした子犬が持っていた何らかのウイルスによって大腸炎を起こし、命が危ぶまれたことがあります。
1週間ほど動物病院のICUに入院しましたが状態が悪く、家で看取った方が良いと退院になったのです。
幸いなことに愛犬は危機を乗り越えることができましたが、ワクチン接種をしていたら症状が軽く済んだかもしれないと考えずにはいられませんでした。
このように、混合ワクチンは狂犬病以外の感染症から愛犬を守るためにも必要なものなのです。
また、日本では一般的にコアワクチンが含まれているのが5種混合以上であることから、トリミングサロンやドッグランでは5種混合以上のワクチン接種証明書の提出を求めているケースが多いため注意してくださいね。
ワクチン接種の副作用(副反応)
ワクチンにはタンパク質や効果を高める物質などが含まれており、ワクチン接種で副反応を起こすこともあります。
| ■ 犬のワクチン接種の副反応
嘔吐 |
接種後すぐに起こるものもあれば、数日後に起こるものもあるため、接種後72時間は愛犬の様子をよく観察してあげることが大切です。
また、副反応の症状が現れたときは、自己判断せずに動物病院を受診しましょう。
老犬のワクチン接種はいつまで必要?獣医師と相談しながら行う
犬にとってワクチン接種はとても大切なことですが、老犬ではいつまで行えばいいのでしょうか。
ワクチンは、病原体を弱めたものや活性を失わせた病原体を体に入れて抗体をつくります。
老犬の体の負担になるのではないかと心配になるのは当然です。
ここでは、老犬のワクチンがいつまで必要なのかを見ていきましょう。
狂犬病ワクチンは基本的にずっと必要
狂犬病ワクチン接種は、法律で義務付けられているため生涯にわたって必要です。
年齢で免除されることはなく、何歳であっても接種しなければいけません。
一方、混合ワクチンは接種が勧告・推奨されていますが、任意のため必ずしも必要というわけではありません。
しかし、トリミングサロンやドッグラン、ペットホテル、ドッグカフェ、犬同伴可能宿泊施設などでは、狂犬病ワクチンだけでなく混合ワクチンを接種していないと利用できないことがほとんどです。
とはいえ、狂犬病ワクチンも混合ワクチンも、身体にとって負担やリスクが大きすぎる場合は接種しないほうが良いと獣医師が判断することもあります。
接種できない場合は予防接種実施猶予証明書をもらう
老犬がワクチン接種をしないほうが良いと獣医師に判断されたら、獣医師に伝えて「予防接種実施猶予証明書」を発行してもらいましょう。
私が実際に作成してもらったものが以下になります。

狂犬病ワクチン接種を行わないと、義務違反で罰則(罰金20万円)を科せられることもあります。
そのため、お住まいの役所で免除申請する必要がありますが、自治体によっては予防接種実施猶予証明書をよく知らなかったり、特に申請書等がなく上の画像のように動物病院で作成してもらう場合もあるので一度確認してみましょう。
また、さまざまな施設を利用する際に、予防接種実施猶予証明書があればワクチン接種をしていなくても利用を承諾してくれるところも多いですよ。
(利用施設に事前にお問い合わせいただくことをおすすめします)
老犬のワクチン接種の負担を減らす方法3つ
老犬のワクチン接種は、副反応のリスクが高まったり、体調不良の原因となることがあります。
狂犬病ワクチンは避けることはできませんが、混合ワクチンは負担を減らしてあげることができるため、獣医師と相談しながらより良い方法で行いましょう。
ここでは、老犬のワクチン接種の負担を減らす3つの方法をご紹介します。
※ご紹介する方法や情報意外にもさまざまな考え方があるため、ワクチンの種類や頻度などは獣医師の指示に従いましょう
コアワクチン接種は3年に1度の頻度にする
世界小動物獣医師会は、コアワクチン(ジステンパーウイルス、パルボウイルス、アデノウイルス)は、3年に一度程度の頻度で接種することが望ましいとしています。
ただ、日本では5種混合ワクチン以上にしかコアワクチンのすべてが含まれていないことがほとんどです。
そのため、ノンコアワクチンも含まれることから毎年接種することが一般的となっていますが、獣医師に相談してできる限り混合ワクチンの接種頻度を少なくするようにしてみましょう。
抗体検査で不要なワクチン接種を避ける
動物病院では、1万円前後で抗体検査を行ってくれるケースがあります。
抗体検査を行うことでどれだけ抗体が体内に残っているかがわかるため、その結果をみて必要なワクチン接種をすることができます。
施設などを利用する際は、抗体検査の結果を提出すれば、ワクチン接種をしていなくても問題ない場合もあります。(事前にお問い合わせいただくことをおすすめします)
ワクチンの種類を見直す
混合ワクチンは動物病院の取り扱いによってさまざまですが、2種混合や5種混合、8種混合や11種混合などがあります。
種類が増えれば予防できる病気も増えますが、その一方で体にかかる負担も大きくなる場合も。
どのワクチンが必要なのかを獣医師とその都度相談しながら決めて、接種のメリットをリスクが上回ると獣医師が判断したワクチンは接種しないようにしましょう。
老犬のワクチン接種の注意点
老犬はワクチン接種による副反応のリスクが高く、若い犬では軽度で済むような症状でも老犬は重い症状が出ることがあります。
そうしたリスクを下げるためにも、老犬のワクチン接種の注意点を知っておきましょう。
体調が良いときに行う
ワクチン接種は、老犬の体調が良いときに行いましょう。
ワクチンは病原体を体に入れて抗体を作るため、体調があまりすぐれないときに接種すると体調不良の原因となる恐れがあります。
体調不良に備えて午前中に行う
老犬に限らずいえることですが、ワクチン接種は午前中に行うようにしましょう。
午前中に接種することで、午後に体調不良や副反応が出ても、すぐに動物病院を受診することができます。
また、接種後は15分〜30分程度動物病院で待機することで、アナフィラキシーショックが起きてもすぐに診てもらうことができます。
| ■ アナフラキシーショックとは?
アレルゲンに反応し、全身に過剰なアレルギー反応が起きてしまうこと。 |
接種後当日は安静に過ごす
ワクチン接種をした当日は、激しい運動やシャンプーなどは控え、安静に過ごしてもらうようにしましょう。
トイレを屋外でしかしない老犬では、トイレをするために散歩に出ることは問題ないですが、早めに切り上げることをおすすめします。
老犬のトイレを屋外から屋内に変えてあげる方法はこちら⇩
|
動物介護士が解説|老犬が外でしかトイレをしない!外から中へ変えてあげる方法 |
まとめ

狂犬病ワクチンや混合ワクチンは、感染症から愛犬を守るためにも大切なものです。
しかし、老犬では体力や回復力が衰えることから、できる限り負担とならないように検討してあげなくてはいけません。
かかりつけの獣医師とよく相談しながら、愛犬にとっての最善策を考えてあげましょう。
\ おすすめサプリメント /
老化や脳ケア、シニア犬のからだ全体の健康維持に役立つ動物病院専用サプリメント「トライザ」の無料お試しサンプルは ↓ から
執筆者:高田(動物介護士)
※ご紹介したワクチン接種についての情報は、参考例です。
ワクチン接種については、さまざまな考え方や個体によって最善策が異なるため、かかりつけ動物病院の獣医師によくご相談ください。
<参考文献>
※:WSAVA(世界小動物獣医師会)