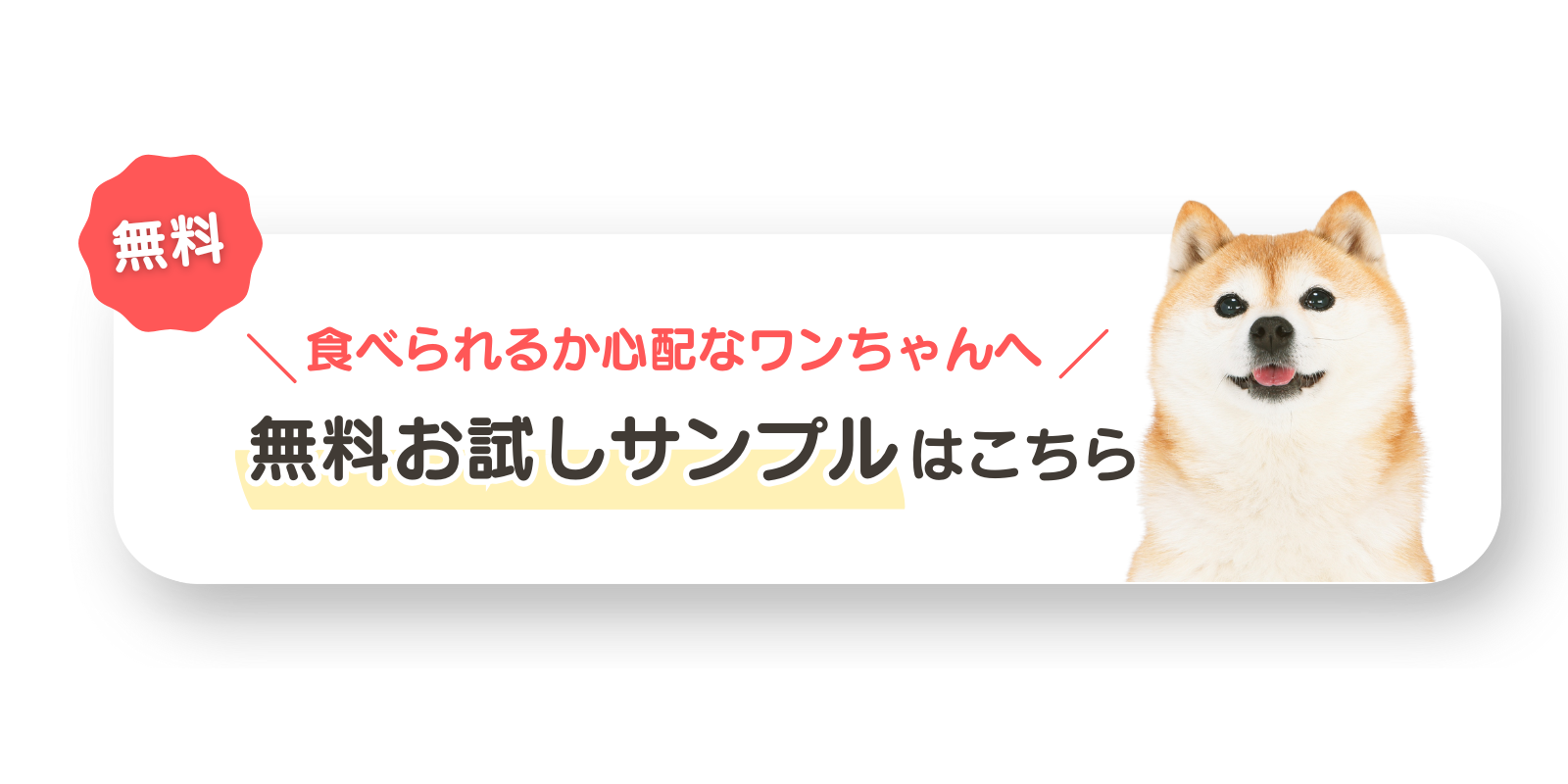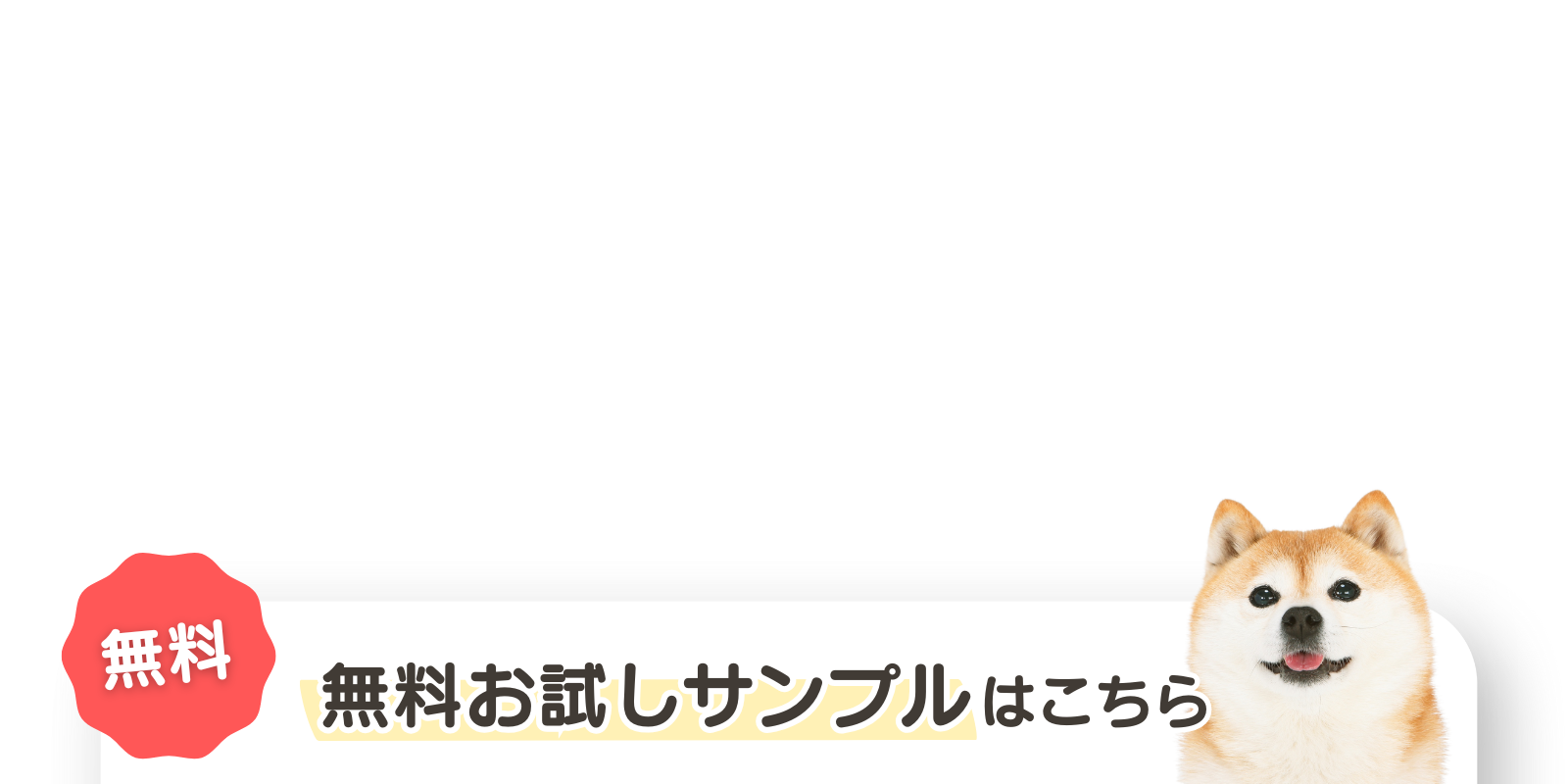動物介護士解説|犬の老化のサインを見逃さないで!7歳をすぎたら要注意

若く元気だと思っていた愛犬も、シニア期に入れば老化のサインが現われはじめます。
いつまでも元気で過ごしてもらうことはもちろん、快適なシニア期を送ってもらうためには、老化のサインを見逃さず、状態に応じたケアをしてあげることが大切です。
今回は、高齢の愛犬たちと暮らしていた動物介護士の私が、犬の老化のサインや老犬と暮らすときに気をつけてあげたいことを解説します。
| 【執筆者保有資格】
動物介護士、ペットフーディスト、犬の管理栄養士 他 |
犬の老化はいつから起こる?何歳からが老犬なの?
犬の老化がいつから起こるかは個体差があるため、一概に「何歳から」ということはできません。
しかし、一般的には小型犬や中型犬では7歳頃から、大型犬は5歳頃からシニア期に入り、寿命の3分の2を過ぎたあたりからハイシニア期(高齢期)に入るとされています。
犬の平均寿命が14.90歳ということをふまえて、愛犬はどのあたりにいるのかを考えてみましょう。
また、老犬になったかは、かかりつけの獣医師に確認してもらうことをおすすめします。
老犬になると食事内容や食事回数を調整する必要がありますが、7歳になったら絶対に老犬用フードを与えなければいけないということではありません。
老犬用フードに切り替える時期や、愛犬の状態に合った適切な栄養素については獣医師に相談しながら決めていきましょう。
|
専門家が解説|老犬のドッグフードの選び方は?押さえておきたいポイント6つ |
|
専門家が解説|老犬の食事回数や食事内容は?食事量や注意点も |
そもそも犬の老化とは?

老化は、犬が身体の発達を終えてから起こる生理機能の衰退です。
老化は元に戻ることはなく、進行し続けます。
老化の進行のスピードに個体差はありますが、すべての犬に起こる変化で、老化によってさまざまな病気にかかりやすくなります。
犬の老化の原因
老化の原因のひとつに、体内での活性酸素の増加が挙げられます。
活性酸素は免疫機能や脳機能、細胞伝達物質など、身体の機能を正常に保つ重要な役割を担っていますが、増えすぎてしまうと細胞にダメージを与えて老化や病気を引き起こします。
身体には、活性酸素が増えすぎないように働く抗酸化防御機能がありますが、加齢と共にその能力が衰えるため、活性酸素が増えてますます老化が加速するという悪循環に陥りやすくなるのです。
老化による犬の身体への影響
老化は、犬の視力や聴力、嗅覚などを低下させます。
さらに、内臓機能や免疫機能、認知機能、嚥下能力、滑膜の弾力など、身体のさまざまな機能が低下しやすくなります。(関節液の減少なども起こりやすくなります)
そのため、関節炎や胃腸炎、肺炎、認知症、心臓病、腎臓病、糖尿病、がんなどの病気にかかりやすくなるため注意が必要です。
老化は進行し続けるため、治したり止めたりすることはできませんが、老化のサインを見逃さず、早めに気づいてケアすることで進行のスピードを緩めることはできます。
犬の認知症については、以下の記事をご覧ください⇩
| 動物介護士が解説|犬の認知症の症状は?予防や対策方法 |
犬の老化のサインは?
犬の老化のサインは、見た目に現われるものと、行動に表れるものがあります。
一緒に暮らしていると気づきにくいものですが、小さな変化や異変を見逃さないように、日頃から愛犬を観察するようにしましょう。
見た目の老化のサイン
|
・明るいところで見ると黒目の部分が白っぽく見える |
愛犬の見た目に現わる老化のサインは、比較的気づきやすい変化です。
もちろん、すべてのサインが現れるわけではありませんが、普段から愛犬をよく観察することで変化に気づきやすくなるでしょう。
また、見た目ではありませんが、口臭がきつくなるなども老化のサインに挙げられます。
3歳以上の犬の80%が歯周病に罹患していると考えられていますが、老犬になると急激に歯周病が進行することも多いため、普段の観察に加えて口臭のチェックもすることをおすすめします。
行動の老化のサイン
| ・名前を呼んでも反応しない
・昼に寝てばかりいる |
犬の老化のサインは、日々の行動にも現われます。
最初は「何となく昼間に寝てばかりいる」「おもちゃで遊ぶことが減った気がする」など“歳をとったから仕方がない”と思いがちな些細な変化ばかりで、気づきにくいかもしれません。
犬は老犬になると、体力の低下から睡眠時間が増えるのは自然なことですが、普段から愛犬の睡眠時間を把握しておくと、老化の進行をより気づきやすくなるでしょう。
老犬の睡眠については、以下の記事も参考にしてみてください⇩
|
動物介護士が解説|老犬が寝てばかりいるのは病気?注意点や気をつけてあげたいこと |
| 動物介護士が解説|老犬が夜寝ないけど大丈夫?原因と対処法 |
老化のサインが病気による症状の場合もあるため要注意!

犬の老化のサインが、実は病気による症状だったということもあります。
この違いは、獣医師でも診察を行わなければ判断が難しいケースが多いため、老化のサインがみられたときは、まずは動物病院を受診することが大切です。
老化のサインがみられる犬の年齢では、適切な治療を受けないと命にかかわる病気にかかっている可能性もあります。
白髪が出てきたり、ヒゲが白くなっただけであれば一般的な老化症状といえますが、それ以外のサインがみられたときは自己判断せず、獣医師に相談することをおすすめします。
※シニア期を迎えたら半年に一度の定期健診をおすすめします
老犬との暮らしで気をつけてあげたいこと

愛犬に老化のサインがみられたら、老犬の仲間入りです。
老犬との暮らしは、それまで以上に気をつけてあげなければいけないことがでてきます。
ここでは、気をつけてあげたいことをまとめてみました。
① 健康への配慮|年に2回の健康診断を受けよう
老犬になると、さまざまな病気のリスクが高まります。
犬はヒトの4倍のスピードで時間が流れているといわれているように、病気になればその進行も早いケースが多いです。
成犬は年に一度の健康診断が推奨されていますが、老犬では最低でも半年に1回は健康診断を受けさせてあげましょう。
また、定期的に健康診断を受けることで、内臓機能など見えない場所の老化の変化にも気づきやすくなります。
加えて、老犬の体調は日々変化します。
「健康診断をしたから大丈夫」ではなく、様子がおかしい、いつもと何か違うと感じたときは、その都度動物病院を受診することが大切です。
老犬と暮らしていくうえで獣医師との関わり合いは密接となり、大きな助けとなります。
些細なことでも相談して信頼関係を築いておきましょう。
② 老化への配慮|エイジングケアをしてあげよう
老化の原因のひとつは、増えすぎた活性酸素による細胞の酸化です。
過剰な活性酸素は、認知症やがんなどさまざまな病気を引き起こす原因になります。
そのため、活性酸素から身体を守る成分や、老犬が不足しがちな栄養素を取り入れ、エイジングケアをしてあげましょう。
| ■ 老犬のエイジングケアに役立つ成分
・ポリフェノール ・カロテノイド ・神経栄養因子様化合物 ・ビタミン |
消化吸収力も低下する老犬では、食材からこれらの成分を摂取するのは大変なので、効率的に栄養が補えるサプリメントを活用することがおすすめです。
犬用のエイジングケアサプリメントはたくさん販売されていますが、なかには成分含有量が少なかったり、根拠がないものも多くあります。
老犬の健康を支えてあげるためにも、動物病院でも販売されているような製品を選ぶようにしましょう。
③ 生活空間への配慮|生活環境を整えてあげよう
老犬になると、体温調整が上手にできなくなったり、足腰が弱ってきたりと、生活空間・環境への配慮も必要になります。
室温や湿度を過ごしやすいように調整してあげるのはもちろん、足腰にかかる負担を軽減するために段差をなくす、滑りにくい床にしてあげるなど、生活環境を整えてあげることが大切です。
フローリングは滑りやすく、犬が常に足を踏ん張らせている状態なので、カーペットやクッションフロアを敷いてあげるといいでしょう。
老犬に元気で長生きしてもらうためのポイントは、以下の記事で詳しく解説しています⇩
|
動物介護士が解説|長寿犬表彰は何歳から?老犬に長生きしてもらうための秘訣も! |
④ 老後への配慮|トイレは室内でできるようにしておこう
外でしかトイレをしない愛犬の場合は、室内でトイレができるようにしておきましょう。
病気になったときはもちろん、毎回トイレをするために外に出るのは老犬の負担となります。
老犬になるとトイレの我慢もしにくくなり、また我慢することも負担となるため、いつでも自由に室内でトイレができるようにしておくといいでしょう。
老犬のトイレトレーニングについては、以下の記事を参考にしてみてくださいね⇩
|
動物介護士が解説|老犬が外でしかトイレをしない!外から中へ変えてあげる方法 |
まとめ

犬の老化のサインは、一緒に暮らしているとなかなか気づきにくいものです。
また飼い主さんとしても、愛犬が歳を取ったことを、少しだけ受け入れがたい気持ちになってしまうかもしれません。
実際、私は愛犬たちが7歳や10歳のときはまだまだ若いと思っていましたが、白髪を見て「老犬になったんだ」と実感しました。
老化は誰にも止められず、すべてのヒトや動物、生きものに必ず訪れます。
愛犬の老化を悲しむのではなく、どんなケアやサポートが良いのか、いかにシニアライフを健康に楽しく過ごせるかに目を向けてみましょう。
老犬には老犬にしかない良さがあり、老犬との暮らしはより素晴らしいものを与えてくれますよ!
\ おすすめサプリメント! /
老化や脳ケア、シニア犬のからだ全体の健康維持に役立つ動物病院専用サプリメント「トライザ」の無料お試しサンプルは ↓ から
執筆者:高田(動物介護士)