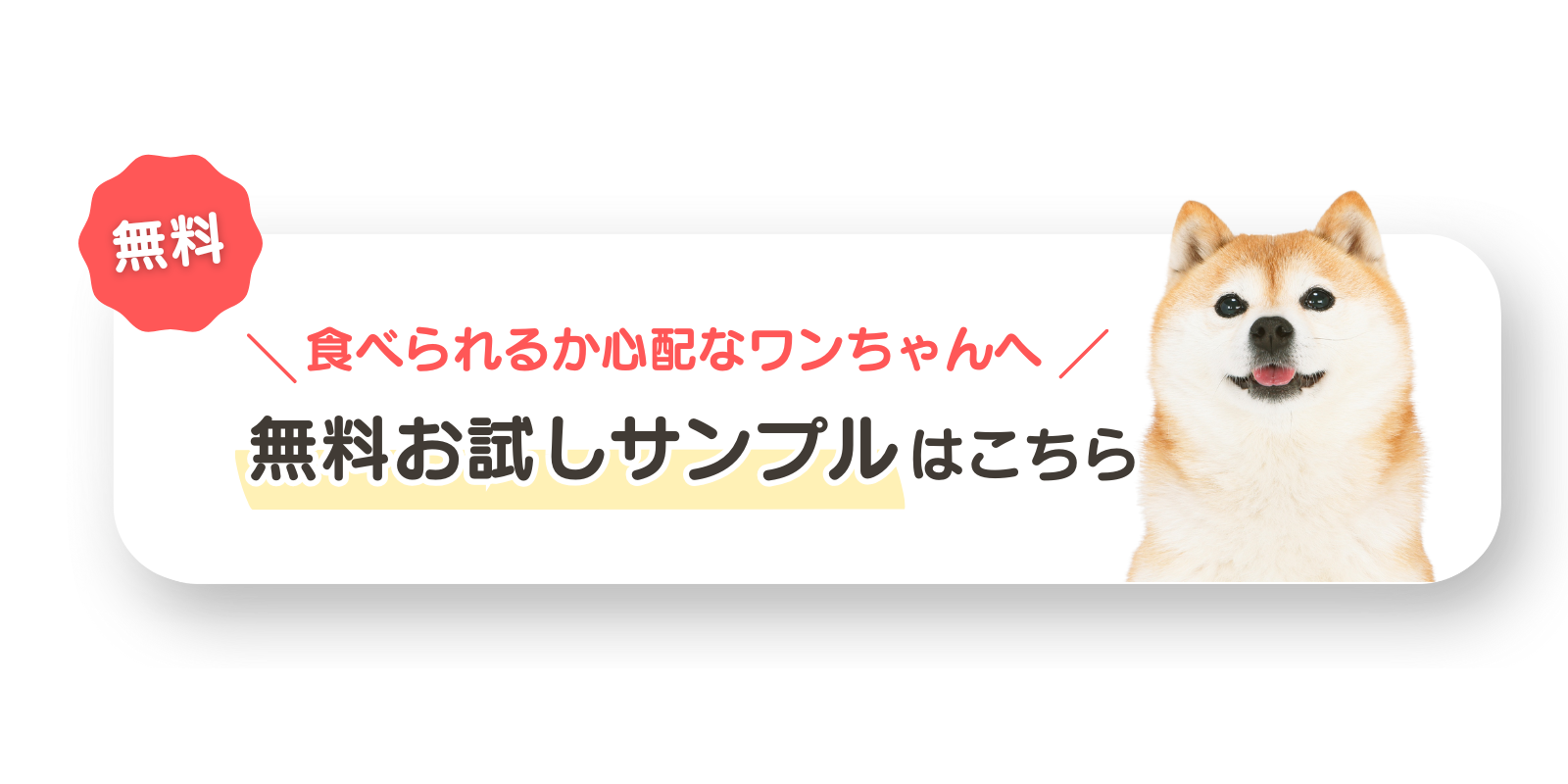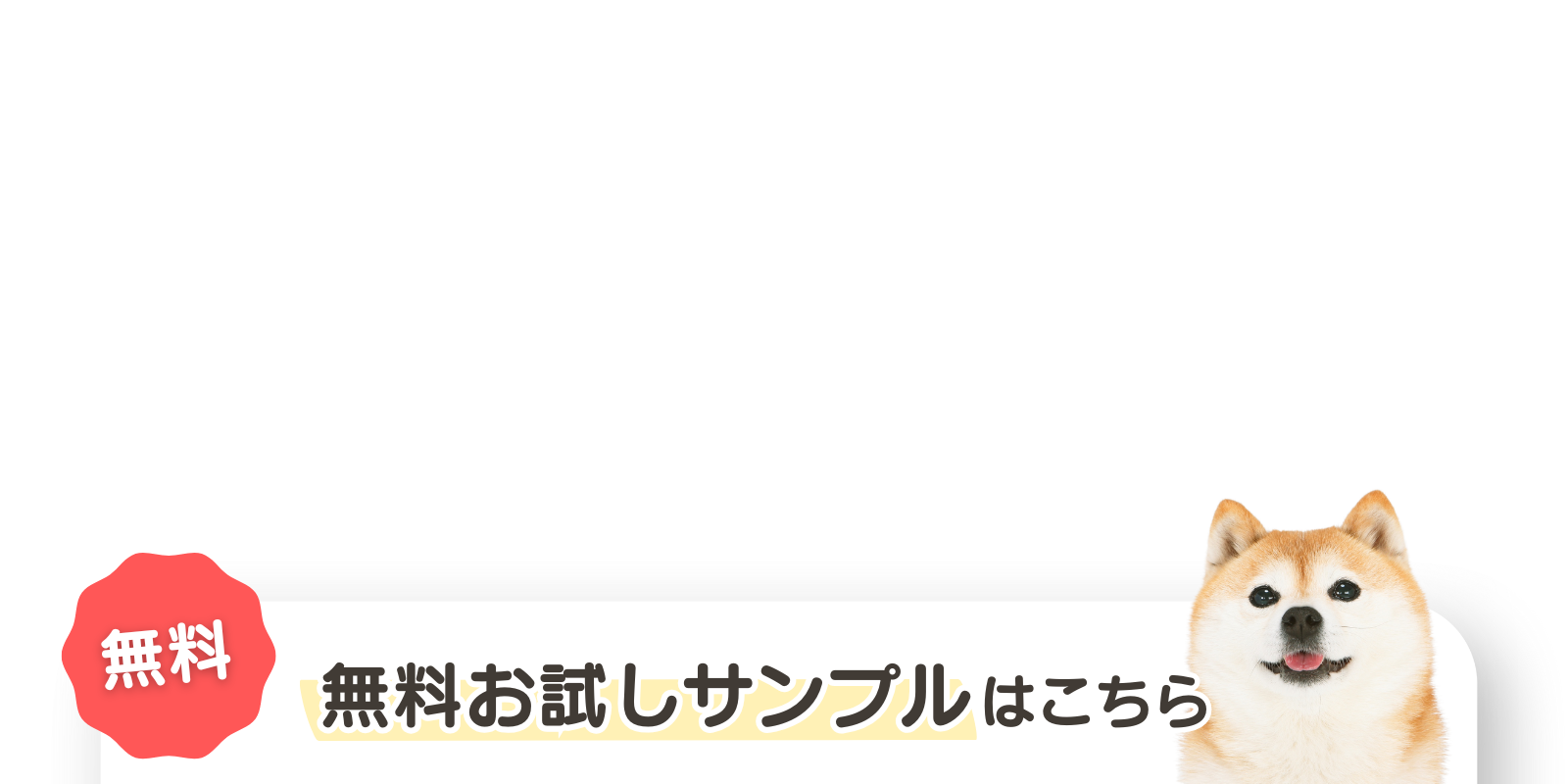動物介護士が解説|長寿犬表彰は何歳から?老犬に長生きしてもらうための秘訣も!

人間では、長寿を祝う年齢や国から贈られる「百歳高齢者表彰」などがありますが、犬にも長寿表彰があることを知っていますか?
そんな制度があるなら、老犬となった愛犬に表彰状をもらいたいという飼い主さんもいるのではないでしょうか。
実際、私もその一人です。
長寿犬表彰や長寿動物表彰は、愛犬を長寿に導いた飼い主さんを讃えるものでもあります。
そこで今回は、長寿犬表彰は何歳からなのか、老犬に長生きしてもらうために何をしたらいいのかをご紹介します。
愛犬にいつまでも元気で過ごしてもらうためにも、ぜひ参考にしてください。
| ■ 執筆者の保有資格 動物介護士、ペットフーディスト、ホリスティックケアカウンセラー 他 |
犬の長寿表彰は何歳から?団体によって異なる

犬の長寿表彰される年齢は、10歳〜18歳以上や15歳以上としているケースが多くみられます。
犬の平均寿命は年々伸びており、ペットフード協会が2024年12月に発表した「令和6年(2024年)全国犬猫飼育実態調査」によると、犬全体の平均寿命は14.90歳です。(※1)
|
■犬の平均寿命(※1) 超小型犬… 15.13歳 小型犬… 14.78歳 中・大型犬… 14.37歳 |
こうしたこともあり、やや高めの年齢に設定されているのかもしれません。
平均寿命を超えた犬は「長生き」や「長寿犬」といえますが、団体によって表彰される年齢は異なるのでしっかり確認して申請しましょう。
日本動物愛護協会の長寿動物表彰|10歳~18歳以上
| 体格 | 体重 | 対象年齢 |
| 小型犬 | ~11kg未満 | 18歳~ |
| 中型犬 |
中型犬
|
15歳~ |
| 大型犬 | 21kg~40kg以下 |
13歳~
|
| 超大型犬 |
41kg~ |
10歳~ |
中型犬や大型犬が老犬になって痩せてしまった場合は、若い頃の体重で判断されるため、体重が満たなくても大丈夫です。

実際に愛犬で申請してみましたが、ダウンロードした年齢・生存証明書を獣医師に記入してもらい、それを公式ホームページのオンライン申請でアップロードするだけと簡単です。
ほかに、愛犬の写真を1枚アップロードします。
動物病院で証明書の作成代は支払いましたが、それ以外に特に費用もかからず、申請してから10日ほどで愛犬の写真入りの長寿表彰状が送られてきました。
寿命はそれぞれ異なるため、本来であれば何歳だから表彰するというものではなく寿命をまっとうすることが大切ですが、日本動物愛護協会では適正飼育と終生飼養を啓発するために表彰年齢を設けて表彰しているそうです。
長寿動物表彰の申請は以下をご覧ください。
ジャパンケネルクラブ(JKC)の長寿犬表彰|15歳以上
一般社団法人 ジャパンケネルクラブの長寿犬表彰は、JKC会員が所有する登録犬(血統証明書のある犬)が15歳以上になると長寿犬表彰を受けられます。
会員で、なおかつ体の大きさに関係なく15歳以上の血統書のある犬と条件が限定されるため、注意が必要です。
表彰を希望する場合は、会報誌の9月号と10月号にお知らせが出るため、郵送やメールで申込みます。

申し込みの締切日が設定されているので、よく確認しましょう。
後日、JKCが発行する会報誌「JKCガゼット」に愛犬のプロフィールと顔写真の掲載があるほか、愛犬の写真入りの長寿表彰状が贈呈されます。
各獣医師会の長寿犬表彰|14歳以上~18歳以上
各都道府県にある獣医師会も長寿犬表彰や長寿犬優良飼養者の認定・表彰を行っています。
対象となる年齢は獣医師会によって異なり、小型犬では16歳以上や18歳以上、中型犬は16歳以上、大型犬は14歳以上、体の大きさに関係なく17歳以上など、さまざまです。
住んでいる地域の獣医師会は何歳からを対象としているのか、確認してみるといいでしょう。
各自治体の長寿犬表彰|15歳~18歳以上
近年は、長寿犬表彰を行う自治体も増えているようです。
下記はほんの一例ですが、対象年齢と主な条件をまとめてみました。
| 市区町村 | 対象年齢 | 条件 |
| 京都市 | 15歳以上 |
・マイクロチップ装着 |
| 名古屋市 | 18歳以上 | 狂犬病注射済票の交付を過去3年間受けている |
| 丹波篠山市 | 17歳に達する犬 | - |
| 安城市 | 17歳以上 | ・市内在住 ・狂犬病注射済票の交付を過去5年間受けている |
| 長野市 |
小型犬:16歳以上 |
- |
狂犬病予防と動物愛護の一環として行う自治体もあれば、終生飼養と適正飼養の普及啓発のために行っている自治体もあり、対象年齢や条件はさまざまです。
住んでいる自治体が長寿表彰を行っているか、チェックしてみましょう。
企業による長寿犬表彰|18歳以上
ドッグフードを製造・販売する企業の中には、ドッグフードを定期購入している18歳以上の犬を対象に長寿表彰を行うこともあります。
毎年行われているわけではなく、取り組みを行っているメーカーも少ないですが、ドッグフードを定期購入している場合はチェックしてみるといいでしょう。
老犬に長生きしてもらうための8つのポイント

ここでは、老犬に元気で長生きしてもらうために必要な8つのポイントをご紹介します。
獣医疫学会が発表した論文では、飼い主さんが健康や飼育環境に配慮した犬のほうが長生きすると結論付けているため(※2)、以下のポイントを参考にしてみてください。
| ■ 老犬に長生きしてもらうための8つのポイント ① 良質でバランスの良い食事を与える ② 老犬が不足しがちな栄養素はサプリメントで積極的に補ってあげる ③ 適度な運動をさせる ④ 質の良い睡眠を取ってもらう ⑤ できる限り室内飼いにし温度管理を徹底する ⑥ 滑りやすい床や段差に配慮する ⑦ シャンプーは手早く終わらせる ⑧ 些細なことでも獣医師に相談する |
それぞれ詳しくみていきましょう。
① 良質でバランスの良い食事を与えよう
老犬の食事は、良質なタンパク質や脂質を使用したバランスの良い食事を与えましょう。
老犬は、成犬よりも良質なタンパク質を多く必要とし、良質なタンパク質は消化吸収にも優れています。
また、ドライフードより手作りごはんのほうが平均32ヶ月長生き、併用しても平均18ヶ月長生きしたという調査結果もあり(※3)、老犬に手作りごはんをあげている飼い主さんも多いのではないでしょうか。
しかし、飼い主さん自身が作る手作りごはんでは栄養が足りていない場合も多く(※4)、栄養不足となる恐れがあるため注意が必要です。
老犬に必要な栄養が不足しないように、栄養バランスが考えられている総合栄養食やFEDIAF(欧州ペットフード工業連合会)の栄養基準を満たしたものを与えるようにしましょう。
また、手作りごはんを与えたい場合は、自分で作るものは一日一食程度にとどめ、総合栄養食のフレッシュフードなどを活用することをおすすめします。
老犬のドッグフードの選び方や与え方については、以下の記事で詳しく解説しています。
|
専門家が解説|老犬のドッグフードの選び方は?押さえておきたいポイント6つ |
② 老犬が不足しがちな栄養素はサプリメントで積極的に補ってあげよう
老犬は、加齢によって体内でつくることができていた栄養素の生産が減ってしまいがちです。
そのため、ドッグフードだけでは補いきれない栄養素や、新たに補ってあげたい成分がたくさん出てきます。
|
■ 老犬が積極的に摂取したい成分 ・抗酸化成分 ・腸内ケア成分 ・関節ケア成分 |
老犬はグルコサミンやコンドロイチンの生成量の減少、腸内細菌の減少(※5)、活性酸素に対する防御機能の低下などが起こりやすく、どれも積極的に摂取したい成分ばかりです。
これらの成分は免疫機能や脳機能の健康にも大きく関係してきます。
ただ、成分含有量が少なかったりエビデンスがないものも多くあるため、動物病院でも販売されているような製品を選ぶことをおすすめします。
我が家の愛犬は、最近注目が集まっているグネチンCとバングレンが配合されたものが体質に合っていたようで18歳と高齢であるにも関わらずとても良かったです。
バングレンは脳の神経幹細胞に働きかけて神経細胞の新生(分化)を促し、新規細胞の成長や維持に深く関与すると考えられている神経栄養因子のような働きをすることがさまざまな試験から明らかになった成分です。
犬の認知症向けのサプリメントは種類が多く選ぶのも大変ですが、愛犬の体質に合ったものを見つけることができれば、認知症のサポートに役立てることができるでしょう。
ただ、成分含有量が少なかったりエビデンスがないものも多くあるため、動物病院でも販売されているような製品を選ぶことをおすすめします。
③ 適度な運動をさせてあげよう
基本的には、老犬であっても毎日散歩に行くことが理想です。
犬によって必要な運動量は異なるため、散歩の時間は愛犬の状態に合わせてその都度判断してあげましょう。
ただ、体調が悪い老犬を無理に連れ出したり、足腰が痛くて歩けない老犬を無理に歩かせることはおすすめできません。
自力で歩くことが難しい老犬や、病気などで体調が不安定な老犬では、ペットカートや抱っこなどで散歩に行くようにしましょう。
運動にはなりませんが、外の空気や音、匂い、目にするものなどさまざまな刺激が老犬に良い影響を与えてくれます。
※獣医師や専門家が必要と判断した場合には、リハビリテーションの一環で運動が推奨されるケースもあります
また、適度に日光を浴びることで脳内の神経伝達物質である「セロトニン」の分泌が促され、体内時計の調整や精神の安定、睡眠リズムの調整、免疫機能の調整に重要なビタミンDの生成促進などが行われます。
このようにさまざまなメリットがあるため、老犬に無理のない範囲で散歩に連れ出してあげましょう。
注意点として、なかには屋外の刺激に敏感でストレスを感じてしまう老犬もいます。
その場合は無理に外に連れ出さず、家の中で運動させてあげたり窓辺で日向ぼっこをしてもらうなど工夫しましょう。
④ 質の良い睡眠を取ってもらおう
睡眠はとても重要な役割があり、睡眠不足は健康にさまざまな悪影響を与えます。
老犬の一日の平均睡眠時間は18〜20時間程度とされているため、十分な睡眠時間を確保してあげたり、質の良い睡眠を取らせることが大切です。
|
■睡眠の役割 ・自律神経のバランス調整 |
適度な運動や日光浴はもちろん、安眠できる環境をつくってあげるといいでしょう。
老犬の睡眠については、以下の記事で詳しく解説しています。
| 動物介護士が解説|老犬が寝てばかりいるのは病気?注意点や気をつけてあげたいこと |
|
動物介護士が解説|老犬が夜寝ないけど大丈夫?原因と対処法 |
⑤ できる限り室内飼いにして温度管理を徹底してあげよう
寒さや暑さ、激しい温度差は老犬の体に負担がかかりやすくなります。
実際、室内で飼われている犬と屋外で飼われている犬では、室内で飼われている犬のほうが寿命が2~3年長いという報告もあります。(※6)
外で飼っている場合は室内で過ごせるように考えてみましょう。
老犬は体温調整が上手にできないため、また室内で飼っている場合でも、温度管理が重要です。
| ■ 老犬に快適な室温や湿度の目安 ・室温…25℃前後 ・湿度…50~60% |
もちろん個体差もあり愛犬の適温を探してあげることが大切ですが、温度差や高温多湿は心身に負担が大きくかかりやすいため注意しましょう。
⑥ 滑りやすい床や段差にも配慮してあげよう
老犬は足腰も弱りがちで、滑りやすい床や段差は足腰に負担をかけてしまうため、床や段差にも配慮してあげましょう。
滑りやすい床にはタイルカーペットやコルクマット、ラグなどを敷いてあげることで負担を軽減してあげられます。
また段差も上り下りが負担となったり、踏み外したりして転んでケガをする可能性もあるため、スロープの設置なども検討してみましょう。
⑦ シャンプーは手早く終わらせよう
老犬もお手入れは大切ですが、シャンプーを行うときは10分〜15分を目安に手早く終わらせましょう。
老犬にとってシャンプーは心身に負担が大きく、体調不良の原因となることもあります。
体調が悪そうなときやお腹の調子が悪いときは無理に行わず、体を拭いてあげるだけでも問題はありません。
できる限り負担をかけないように配慮してあげることが大切です。
老犬のシャンプーについては、以下の記事を参考にしてみてください。
| 動物介護士が解説|老犬のシャンプーの頻度は?注意点や負担をかけないポイントも |
⑧ 些細なことでも獣医師に相談しよう
老犬では、最低でも半年に一回の健康診断をおすすめします。
ただ「健康診断で異常がなかったから大丈夫」ではなく、違和感があったり気になることがあった場合は、些細なことでも獣医師にご相談ください。
老犬に限らず、犬は痛みや不調を隠そうと我慢してしまう生きものです。
明らかに調子が悪そうという頃には病気が悪化・進行している場合もあります。
老犬では、体力の衰えから病気になっても回復に時間がかかるほか、軽度な病気が深刻な状態になってしまうことも珍しくありません。
たとえ大きな病気が見つかったとしても、QOL(生活の質)を保つことが愛犬の「元気で長生き」に繋がります。
病気の早期発見・早期治療はとても大切であることはもちろん、老犬では獣医師との連携が欠かせないことも多いです。
スムーズな連携や信頼関係を築いておくためにも、些細なことでも動物病院に行くクセをつけておくといいでしょう。
まとめ

犬の寿命は年々伸びており、長寿表彰の年齢を引き上げたところもあるほどです。
長寿表彰のハードルは高いですが、それをひとつの目標にすることもできるのではないでしょうか。
実際、私は4匹の老犬と暮らしていましたが、長寿表彰されたのは一匹の愛犬だけです。
しかし、年々長寿表彰を行う自治体や獣医師会も増え、チャンスはたくさんあります。
表彰状をもらえたときは感慨深く、長生きしてくれている愛犬に改めて感謝することでしょう。
老犬になった愛犬のお世話は、「長生きしてもらうための8つのポイント」も参考にしてみてくださいね。
\ グネチンCとバングレンが一緒に摂れる /
老化や脳ケア、シニア犬のからだ全体の健康維持に役立つ動物病院専用サプリメント「トライザ」の無料お試しサンプルは ↓ から
<参考文献>
※1:一般社団法人 ペットフード協会「全国犬猫飼育実態調査」
※2:獣医疫学会「犬と猫における長寿に関わる要因の疫学的解析」
※3:Cavalier Health「Relation between the domestic dogs’ well-being and life expectancy statistical essay」
※4:「CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS「Evaluation of the owner's perception in the use of homemade diets for the nutritional management of dogs*」
※5:Bioscience of Microbiota, Food and Health「Transition of intestinal microbiota of dogs with age」
※6:公益財団法人どうぶつ基金「外飼いはやめよう。犬猫も寒いのだ!」
執筆者:高田(動物介護士)