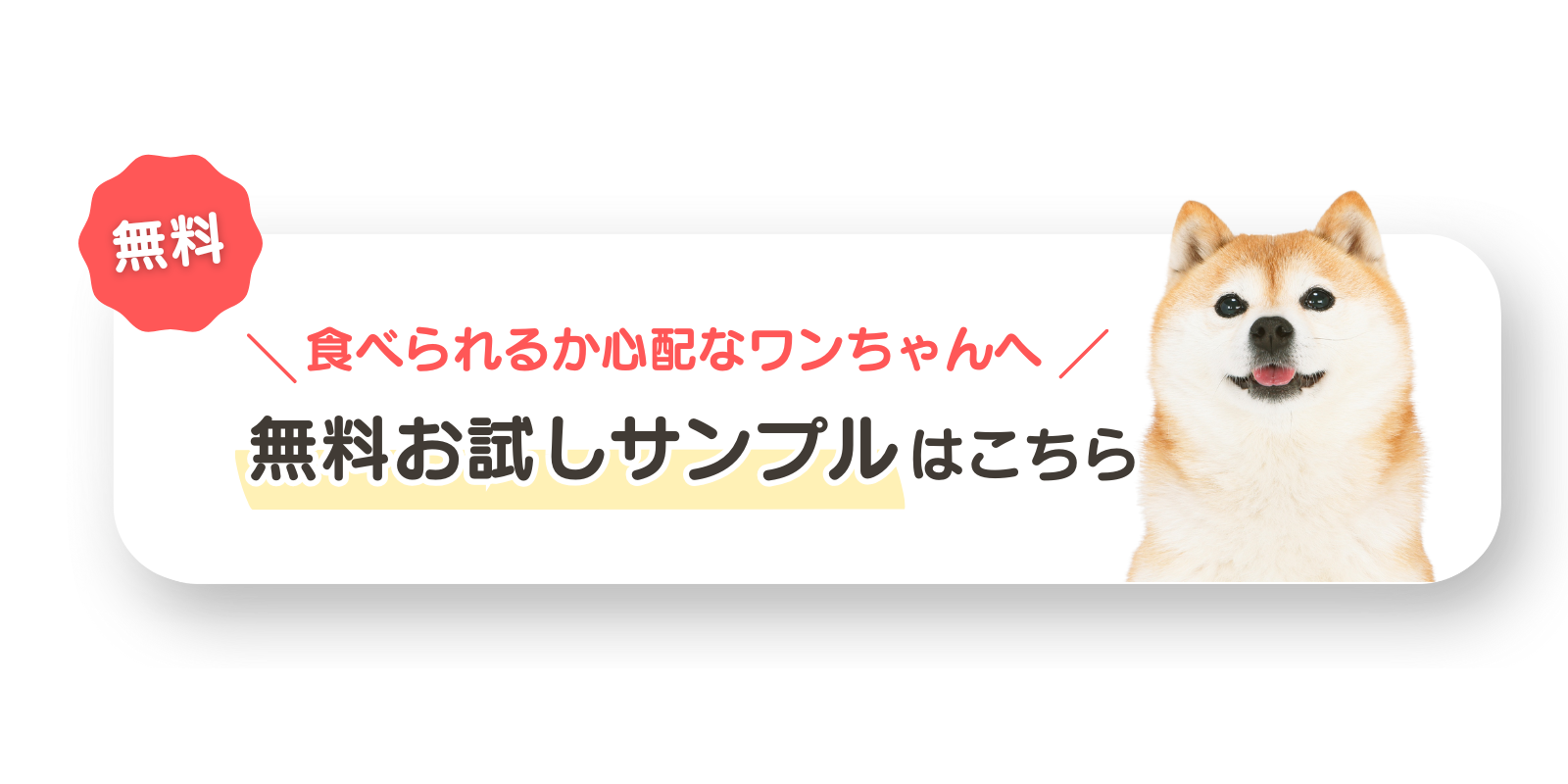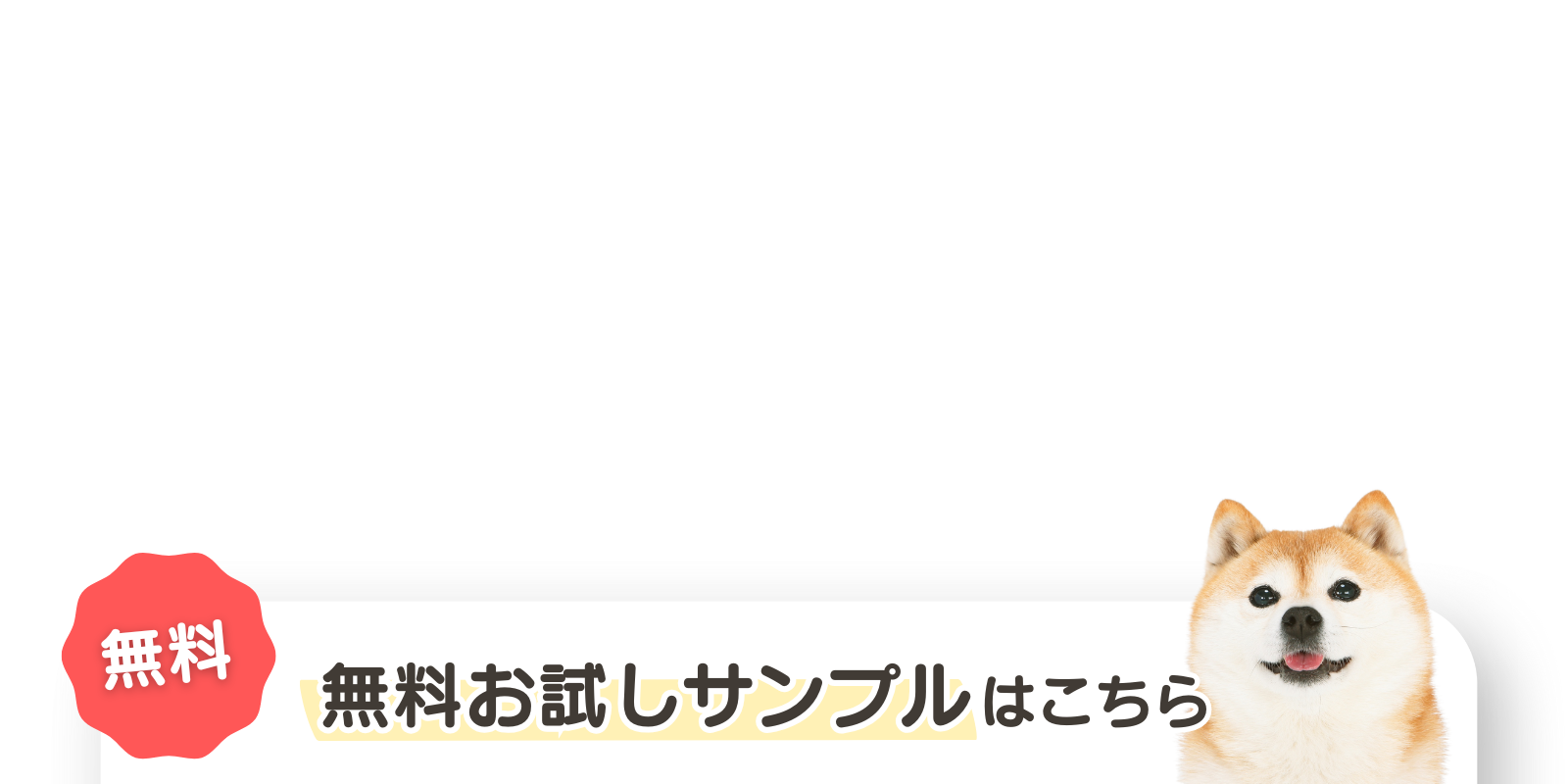動物介護士解説|犬の夜鳴きをどうにかしたい!原因別対策法と注意点

愛犬が夜鳴きをするようになり、近所迷惑の心配や自身の寝不足、家族間の不和などで頭を悩ませているのではないでしょうか。
夜鳴きにイライラして、つい愛犬につらくあたってしまい、後になって後悔することもありますね。
実際に、私も愛犬の夜鳴きに悩んだことのあるひとりです。
しかし、考えかたを変えて違う目線で見てみると、どうしたら良いのかが分かり夜鳴きに悩まされることはなくなりました。
そこで今回は、長年人間の介護に携わり現在は動物介護士である私が、犬の夜鳴きの原因と対策法を解説します。
長生きしてくれている愛犬に穏やかに接することができるよう、ぜひ参考にしてくださいね。
そもそもなぜ犬が夜鳴きをしているのか考えてみよう
犬はシニアになると、身体のあちこちの機能が衰えてきます。
| ■ 犬のシニア期の目安
・小型犬・中型犬…7歳ごろから |
老化のスピードは個体差がありますが、年を重ねるごとに老化が進んでいくのはヒトも犬も同じです。
もしも自分が思うように体を動かせなくなったり、体のどこかに不調がある、誰かの助けがなければ水も飲めない、トイレもできないとなったら、不安やもどかしさを感じたり、誰かを呼ぶのに声を出したりしませんか?
言葉が話せないだけで、犬も同じなのです。
また、認知症も認知機能の低下などによって不安や恐怖を感じやすくなったり、脳の機能が低下することで夜鳴きを起こす要因になります。
このように、犬の夜鳴きにはさまざまな要因があります。
なぜ愛犬が夜鳴きをしているのか考えてあげることは、夜鳴きの対策には不可欠です。
夜鳴き=認知症と思われがちですが、必ずしも認知症というわけではなく、原因を突き止めて原因に合わせて対処してあげることが何よりもの対策といえるでしょう。
老犬の夜鳴きで薬を検討している場合は、以下の記事も参考にしてみてくださいね⇩
|
動物介護士が解説|老犬の夜鳴きに薬は効く?使用するリスクや対処法 |
【対策は?】犬の夜鳴きの原因と対処法

シニアになった犬の夜鳴きは、わがままで鳴いているケースは少なく、何らかの理由がある場合がほとんどです。
また、何らかの病気が原因で夜鳴きをしていた場合では、放置してしまうことで悪化させてしまう恐れがあるため、夜鳴きの原因をしっかり探ってあげることが大切です。
ここでは、犬の夜鳴きの原因と、原因に合わせた対処法をご紹介します。
夜鳴きの原因① お腹が空いた・喉が渇いた
夕食から朝食までの時間が長い、食事量が適切ではない場合、お腹が空いて夜鳴きをすることがあります。
水を飲む器が下げられていたり、自分で水を飲めない場合では、喉が渇いているということもあるでしょう。
老犬は消化機能の衰えから、一度に食べられる量が少なくなりがちです。
また、食べるために前のめりになる姿勢は前足を踏ん張らせなくてはいけませんが、その姿勢を維持することが辛く、途中で食べることをやめてしまうこともあります。
そのため、夜中にお腹が空いて夜鳴きをしてしまうのです。
空腹や喉の渇きで夜鳴きをする場合の対処法
空腹時間が長くならないように、 寝る前に食事をさせてあげるなどの時間変更はもちろんですが、一回に食べられる量も少なくなるため、一日の食事回数を増やしてあげましょう。
食べる姿勢がつらくないように、高さのある食器台などを用意してあげることも大切です。
また、いつでも水を飲めるようにしてあげるだけでなく、あまり移動しなくてもすぐに水が飲めるように寝床のそばに水が入った器を用意してあげたり、寝る前に水分補給をしてあげると良いでしょう。
|
専門家が解説|老犬の食事回数や食事内容は?食事量や注意点も |
夜鳴きの原因② トイレに行きたい
昼間は自力でトイレに行ける犬でも、夜間は暗くて不安、見えなくてトイレの場所がわからない、足腰が痛くてトイレまで行けないなどの理由から夜鳴きをすることがあります。
また、トイレをしたいのに出ない、ちゃんと出なくて気持ち悪いなど、排泄に関する場合もあります。
ただでさえ老犬は、膀胱など排泄に関わる機能の低下からトイレの回数が多くなりがちです。
胃腸も弱くなるため下痢や軟便をしやすい上に、トイレでの踏ん張る姿勢がきついなど、トイレ1つを見てもさまざまな原因があるのでよく観察して判断してあげましょう。
トイレ関連で夜鳴きをする場合の対処法
寝床からトイレまでの道筋にジョイントマットなどを敷いて、トイレの場所をわかりやすくしてあげましょう。
ジョイントマットはカーペットやコルクなどの滑りにくいものにしてあげると、歩くときにかかる足腰の負担も軽減してあげられます。
また、寝る前に排泄が済ませられるように誘導したり、夜間だけ排泄の介助をしてあげるといいでしょう。
出きらない、スッキリしないなどが原因の場合では、まず獣医師に相談することをおすすめします。
| 動物介護士が解説|老犬が外でしかトイレをしない!外から中へ変えてあげる方法 |
夜鳴きの原因③ 睡眠環境に問題がある
犬の夜鳴きは、睡眠環境に問題がある場合でも起こります。
老犬は体温調整がうまくできなくなるため、暑い・寒いなど温度が適していなかったり、寝床が硬く体が痛くて眠れないなどの不快感を鳴いて訴えているのかもしれません。
さらに、老犬は年を重ねるごとに我慢ができにくくなったり、こだわりが強くなる傾向があります。
眠る場所が明るすぎる、ヒトの声やテレビの音がうるさすぎる、ヒトの出入りが頻繁で落ち着かないといったことも、安眠できないとして夜鳴きする原因になっている場合もあります。
また、実際に寝たきりの愛犬であったのは、身体の向きを変えてほしい、寝る場所が気に入らない、枕がほしいなどの訴えによる夜鳴きでした。
睡眠環境を見直してみると同時に、どんなタイミングで愛犬が夜鳴きをしているのか観察してみることをおすすめします。
睡眠環境が悪くて夜鳴きをする場合の対処法
犬が安眠できるように、薄暗く落ち着ける場所に寝心地の良い寝床を用意してあげましょう。
体圧を分散してくれる低反発マットなら、寝心地が良いだけでなく、床ずれ(褥瘡)の予防もできておすすめです。
また、落ち着ける場所は、静かな場所を好む犬、飼い主さんのそばを好む犬などその犬によって異なるので、愛犬の落ち着ける場所を探してあげましょう。
さらに、愛犬にとって快適な室温になるように寝床のそばの低い位置に温湿度計を設置し、室温を調整してあげると良いでしょう。
| ■ 犬が快適に過ごせる温度の目安
室温…25℃前後 |
犬にとって睡眠はとても大切です。
快適な睡眠がとれるように、できる限り配慮してあげてくださいね。
老犬の睡眠については、以下の記事で詳しく解説しています⇩
|
動物介護士が解説|老犬が夜寝ないけど大丈夫?原因と対処法 |
|
動物介護士が解説|老犬が寝てばかりいるのは病気?注意点や気をつけてあげたいこと |
夜鳴きの原因④ 痛みや不調がある
何らかの痛みや不調によって、夜鳴きをしていることもあります。
老犬は体力の低下や免疫力の低下から病気や不調をきたしやすく、また回復するのに時間もかかります。
| ■ 痛みを起こす主な原因
ケガ |
痛みを起こす原因はさまざまですが、特に老犬は関節や内臓の病気で慢性的な痛みを抱えていることも多く、鳴いて訴えている可能性があります。
また、痛みではないものの身体の異変や違和感など何らかの不調を感じていることも考えてあげなければいけないでしょう。
痛みや不調で夜鳴きをする場合の対処法
痛みや不調で夜鳴きをしている場合では、早めに動物病院を受診して適切な治療を受けることで夜鳴きは落ち着きます。
飼い主さんが愛犬の痛みや不調を十分に取り除いてあげることはなかなか難しいため、愛犬が夜鳴きをするようになったら一度獣医師にご相談ください。
夜鳴きの原因⑤ 認知症
犬の認知症と夜鳴きの関連性は、実ははっきりとしたことはわかっていません。
しかし、認知症になるとこれまで以上に不安を強く感じやすくなったり、脳が興奮状態に陥りやすいことから、夜鳴きをすることもあります。
| ■ 犬の認知症の主な症状
・夜鳴きをする |
ただ、愛犬が認知症かどうかを飼い主さんが判断することはできません。
上記のような症状はほかの病気でもみられることがあるため、気になるの症状がある場合は一度動物病院を受診することをおすすめします。
認知症で夜鳴きをする場合の対処法
認知症で夜鳴きをする犬は、日中に寝すぎている場合では散歩で適度に疲れさせたり、日光浴をして体内時計と生活リズムを整えてあげましょう。
不安で夜鳴きをしている場合では、飼い主さんのそばで寝させてあげたり、優しく声掛けしながら撫でてあげるなど、不安を和らげてあげると良いでしょう。
私には認知症になった愛犬もいましたが、子守唄を歌いながら撫でていると安心するのか寝てくれていましたよ。
また、脳・老化ケアに役立つ成分が含まれたサプリメントで栄養を補給してあげることも効果的です。
認知症はどんどん進行する病気のため、定期的に動物病院を受診して、愛犬の状態に合わせた治療やケア方法、アドバイスを獣医師から受けることも大切です。
犬の認知症については、以下の記事も参考にしてみてくださいね⇩
|
動物介護士が解説|犬の認知症の症状は?予防や対策方法 |
|
動物介護士が解説|犬の認知症を治すことはできる?治療法やできるサポート |
犬の夜鳴きの注意点
 犬が夜鳴きをするときは、自己判断することなく動物病院を受診することが最も重要ですが、それ以外にも注意することがあります。
犬が夜鳴きをするときは、自己判断することなく動物病院を受診することが最も重要ですが、それ以外にも注意することがあります。
ここでは、犬の夜鳴きの注意点を解説します。
夜鳴きをしても絶対に叱らない
犬が夜鳴きをしても、絶対に叱らないようにしましょう。
イライラしたり、叱りたくなってしまう気持ちはわかりますが、夜鳴きにはさまざまな原因があり、何らかの意味や愛犬からのSOSが込められているケースが多くあります。
叱っても夜鳴きが止まるわけではなく、飼い主さんの気持ちに同調して、ますます夜鳴きが悪化してしまいます。
近所迷惑が心配な場合は、あらかじめお詫びの手紙を用意して、近所のお宅のポストに投函しておくと良いでしょう。
飼い主さん自身が根詰めすぎない
冒頭でも触れましたが、犬の夜鳴きは寝不足や家族間の不和などを引き起こしやすいです。
一生懸命に何とかしようと根詰めすぎると、飼い主さん自身がダウンしてしまうでしょう。
たまには動物病院に預かってもらったり、老犬ホームのショートステイを利用して、息抜きをすることも大切です。
また、どんなことでも獣医師や看護師、動物介護士などの専門家に相談することで、気持ちはずっと軽くなりますよ。
目に見えない体の中からもケアしてあげる
犬の夜鳴きの原因は、身体的・精神的な不調や病気、認知症によるものなどさまざまです。
対処法も状況によってさまざまですが、犬が不足しがちな栄養を補って体や心の健康を維持してあげることで、意外にも夜鳴きの軽減・解消につながることがあります。
特に老犬が積極的に摂取したい栄養素は、活性酸素から体を守る成分や、脳ケア成分、加齢によって体内の産生量が減ってしまう腸内ケア成分や関節ケア成分、ビタミンなどです。
|
■ 老犬が積極的に摂取したい栄養 ・抗酸化成分 ・腸内ケア成分 ・関節ケア成分 ・ビタミン類 |
これらの成分を食材から摂取するのは難しいため、サプリメントで効率的に補ってあげると良いでしょう。
犬用のサプリメントはたくさん販売されていますが、成分含有量が少なかったり、エビデンスがないものも多くあるのも事実です。
そのため、動物病院でも販売されているような製品を選ぶと安心でしょう。
まとめ

犬の夜鳴きの近所迷惑の対策として、雨戸を閉めたり窓に防音シートを貼ることで多少は外に漏れる夜鳴きの声も軽減されるでしょう。
しかし、根本的な対策にはなりません。
犬の夜鳴きは、原因を探ってその原因に合わせて対処してあげることが何よりも大切です。
また「もし自分が愛犬と同じような状態だったら」と考えてみると、どうしてあげたらいいかが分かったり、接しかたが穏やかになり、それが愛犬に伝わって夜鳴きが和らぐこともあります。
犬の夜鳴きはとても大変ですが、おひとりで悩まず、獣医師に相談しながら適切に対処していきましょう。
\ おすすめサプリメント! /
老化や脳ケア、シニア犬のからだ全体の健康維持に役立つ動物病院専用サプリメント「トライザ」の無料お試しサンプルは ↓ から
執筆者:高田(動物介護士)