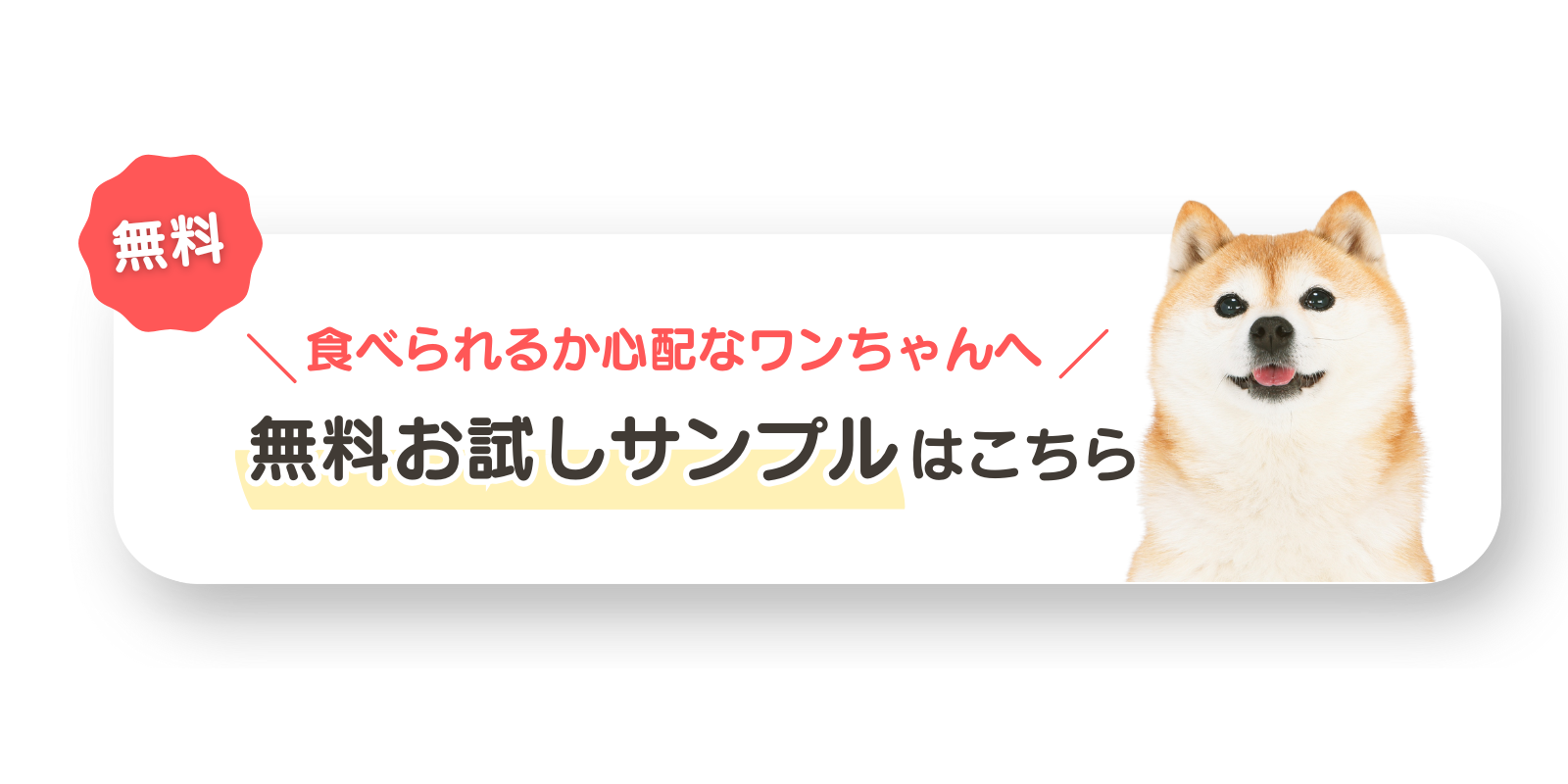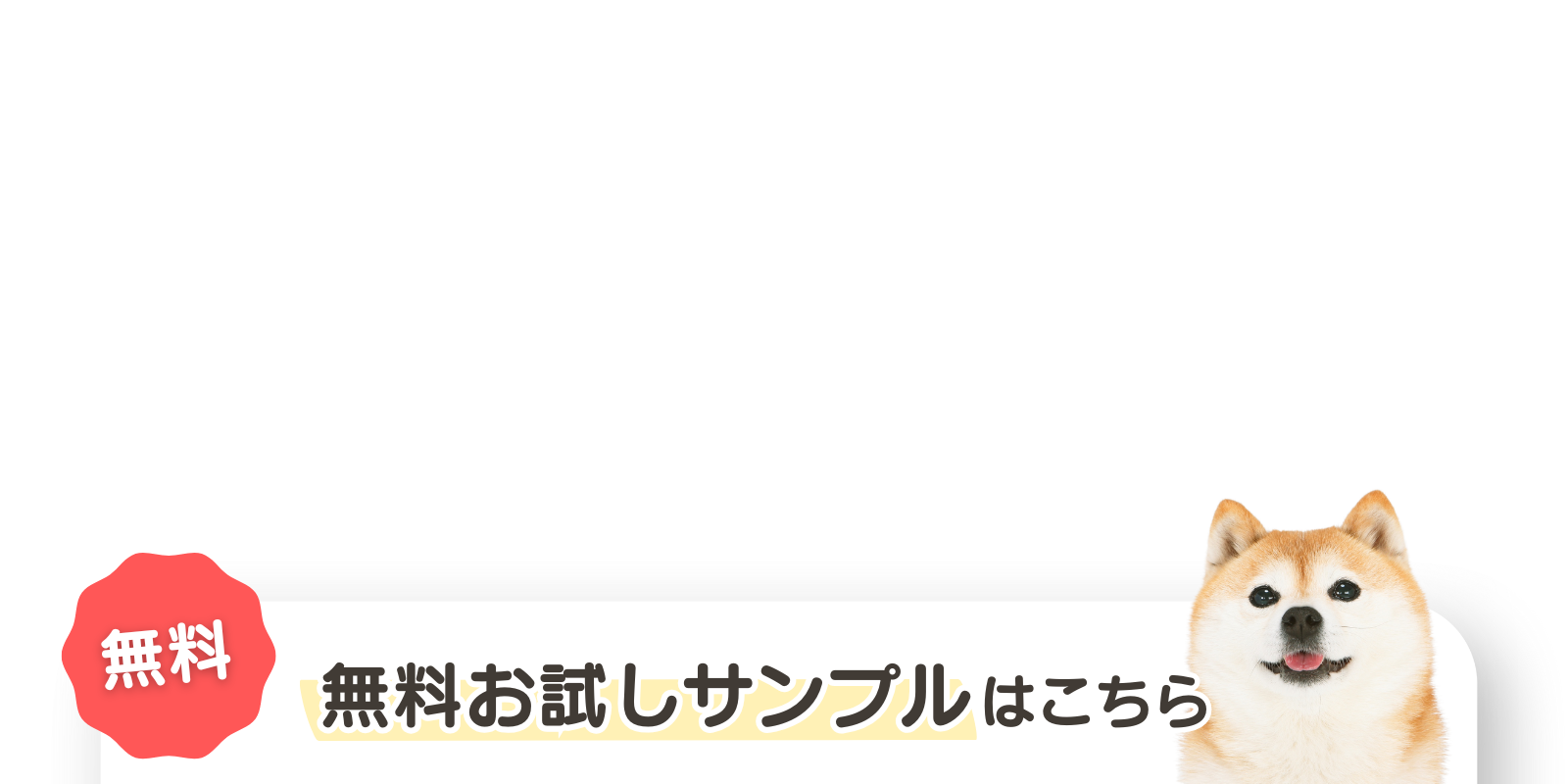犬のてんかん発作とは?症状・対処法や病院に行くべき目安と前兆を解説

愛犬が突然けいれんのような発作を起こしたら、パニックになってしまいますよね。
てんかん発作中はどうしてあげたらいいのか、命に関わるのではないか、予防できるのかなど、知りたいこともたくさんあるでしょう。
実際、私の愛犬(ミニチュアダックス・享年16歳)もてんかん発作を頻繁に起こしていましたが、初めててんかん発作を見たときはこのまま亡くなってしまうのではないかと本当に怖くなりました。
そこで今回は、犬のてんかん発作について解説します。
症状や対処法はもちろん、病院に行くべき目安や前兆もご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
犬のてんかん発作とは?脳の神経細胞が過剰に興奮して起こるもの
てんかん発作は、脳の神経細胞が過剰に興奮することで引き起こされる症状で、脳の一部分の興奮で起きる「焦点性発作」と脳全体の興奮で起きる「全般発作」があります。
てんかん発作は長く続いたり繰り返すことで脳にダメージを与える可能性が高まるため、早期発見・早期治療が大切です。
犬のてんかん発作について、もう少し詳しく知っておきましょう。
犬のてんかん発作の原因
犬のてんかんは、大きく「特発性てんかん」「構造的てんかん」の2つに分けられ、その原因も異なります。

特発性てんかん
遺伝的要因が疑われるが、検査をしても異常は見つからず原因を特定することは困難
構造的てんかん
脳炎、脳腫瘍、脳梗塞、脳出血、頭部外傷など、検査で脳に異常が認められるもの
またこの他に「反応性発作(反応性てんかん)」があり、原因が低血糖、腎不全、肝不全、ミネラルの異常、中毒など、脳に異常はなく二次的に脳に興奮を起こしてしまうものです。
原因を特定するためには、血液検査や脳波検査、MRI検査などが必要となるため、初めて犬にてんかん発作が起きたときは早めに動物病院を受診することが大切です。
また、高齢になると持病などによって全身麻酔が必要となるMRI検査が受けられなくなることもあります。
実際、享年16歳の愛犬は腫瘍で全身麻酔が不可、享年17歳の愛犬も腎臓病で全身麻酔が不可となり、MRI検査ができずにてんかん発作の原因を突き止めることはできませんでした。
原因がわかれば、より適切な治療を受けられる可能性が高まるため、全身麻酔をかけても問題がない状態のうちに、検査を受けておくことをおすすめします。
犬のてんかん発作の症状
犬のてんかん発作の症状は、と「全般発作」「焦点性発作」で異なります。

全般発作(全身の発作)の主な症状
- 全身がこわばってピクピクする
- 手足を突っ張らせながら全身が痙攣する
- よだれや白い泡が出る
- 尿失禁・便失禁する
- 意識を失って急に倒れる など
全般発作は、体全体の症状がみられるため、飼い主さんも気づきやすいでしょう。
意識がなく、飼い主さんの呼びかけにも反応しないため、初めて全般発作を見た場合はパニックになりがちです。
焦点性発作(部分的な発作)の主な症状
- 顔面の1部がピクピクする
- 顔面の痙攣
- 1本の足だけがひきつる
- 頭をガクガクさせる
- 嘔吐する
- よだれが多く出る
- 瞳孔が開く
- 不安が強くなる
- 落ち着きがなくなる
- 宙を噛むようなしぐさをする(ハエ噛み行動)など
焦点性発作は体の一部分のみの症状しかみられず、意識も正常なことが多いため、飼い主さんが気づきにくいです。
また、焦点性発作から全般発作に移行することもあります。
犬のてんかん発作は、その犬によって症状に一定のパターンがある傾向にあります。
犬のてんかん発作の治療
てんかん発作は長く続いたり繰り返すことで脳にダメージを与える可能性が高まるため、できる限り発作を起こさせないように抗てんかん薬でコントロールする治療が一般的です。
脳の病気などが原因でてんかん発作が起きている場合では、その病気に対する治療も並行して行われます。
抗てんかん薬による治療が始まった場合は、自己判断で薬を飲ませるのを止めたり薬を減らすことは絶対にNGです。
急に飲ませるのを止めてしまうと発作がひどくなることもあるので、獣医師の指示に従った回数や量で投与しましょう。
犬のてんかん発作の対処法と注意すること
犬のてんかん発作が起きたときは、慌てず冷静に対処することが大切です。
できれば発作の持続時間の記録と動画を撮影して、動物病院を受診するときに獣医師に見せることで診断のサポートにもなります。
| ■ 犬のてんかんの対処法と注意点
・犬の周りの障害物を取り除き、ケガをしないように安全を確保する |
パニックになって、つい大きな声で名前を呼んだりしがちですが、てんかん発作を誘発することになってしまうため、刺激を与えないようにしましょう。
また、舌を噛まないようにと口にタオルを入れたり、無理に体を押さえつけたりするのも危険です。
口にタオルを入れると窒息する恐れがあるほか、てんかん発作中は犬の意識がない状態や周りの状況がわからない状態なので、飼い主さんが噛まれてケガをしてしまうこともあります。
てんかん発作が起きたときは、発作が落ち着くまでそばに寄り添い、そっと見守ってあげましょう。
てんかん発作後の対処法
犬のてんかん発作後には、数時間にわたって以下のような発作後現象がみられることがあります。
- ウロウロと歩き回る
- 人や自分のいる場所がわからなくなる
- ボーっとしている
- 長時間寝る
- 食欲旺盛になる など
徐々に普段の状態に戻っていくため深く心配することはありませんが、この間の見守りも大切です。
発作後に体が熱くなっている場合は、濡れタオルをかけて冷やしてあげましょう。
また、てんかん発作後すぐに勢いよく水を飲んだりご飯を食べることもありますが、まだ意識がしっかりしていない状態で飲み込む力も低下していることから誤嚥のリスクがあります。
水やご飯を与えるのは、発作が完全に落ち着いてからにしましょう。
ちなみに、てんかん発作は脳のエネルギーを多く消費します。
脳の栄養補給にはちみつなどを少量舐めさせてあげるのも良いですよ。
私は、はちみつレモンを作って舐めてもらっていました。
(食物アレルギーがある場合は、獣医師にご相談ください)
犬のてんかん発作|病院に連れて行く目安

犬のてんかん発作で病院に連れて行く目安は、以下になります。
| ・初めててんかん発作を起こした
・半年のうちに2回目のてんかん発作が起きた |
この中で緊急性があるものは、5分以上続いている場合や発作が治まる前に次の発作が始まる、24時間以内に2回以上の発作が起こる場合です。
通常、犬のてんかん発作は直接命に関わるようなことはありませんが、この場合は重篤な状態で命に関わるケースがあるため、夜間であっても速やかに動物病院を受診することが大切です。
犬のてんかん発作の前兆や発作が起こりやすいタイミング
犬のてんかん発作と付き合っていくうえで、獣医師から処方される薬でのコントロールはもちろん、発作の前兆や起こりやすいタイミングを知っておくことが大切です。
ここで詳しくみていきましょう。
数時間~数日前から前兆がある場合もある
犬によっては、てんかん発作が起きる数時間〜数日前に以下のような行動の変化(前駆症状)がみられることがあります。
| ・落ち着きがなくなる ・イライラしている ・不安感が強くなる ・口をクチャクチャさせている ・ボーっと宙を見つめている など |
ただし、こうした前兆はてんかん発作を起こすすべての犬にみられるわけではなく、またみられたとしてもほかの病気が関連している可能性もあるため、一度獣医師にご相談ください。
夜間や明け方の睡眠時に起こりやすい
犬のてんかん発作は、夜間や明け方などの睡眠時や休息時に起こりやすいです。
そのため、犬が寝ているときに発作が起きても危なくないように、寝床の安全対策を行ってあげましょう。
また、犬によっては強い光や金属音で発作が誘発されてしまうこともあるため、てんかん発作がどんなタイミングで起きるかを記録しておくと、起こりやすいタイミングが大体分かるようになります。
気圧や気象の変化にも要注意
犬のてんかん発作は気圧の変化とも関係があり、曇りや雨の日など気圧が低くなると誘発されることがあります。
人間では寒い日よりも暖かい日の方が発作を起こしやすいという報告もあり、気圧や気象の変化を確認しておくことで予め安全な場所を用意するなどの対策ができるでしょう。
また、多くの老犬の飼い主さんがてんかん発作や認知症の対策に活用している気圧予報のアプリを活用するのもおすすめです。
私も利用していましたが、かなり役立ちましたよ!
|
【気圧予報アプリ 頭痛ーる】 |
てんかん発作を起こす犬は認知症対策も重要!

てんかん発作は、発作の時間が長かったり何度も繰り返すことで脳がダメージを受け、認知症を発症しやすくなるという報告があります。
認知症を発症するとてんかん発作が起こりやすくなるとも言われており、認知症とてんかんの関係性は深いと考えられています。
そのため、悪循環を防ぐためにも、てんかん発作を起こす犬は抗てんかん薬による発作のコントロールだけでなく認知症対策も重要になります。
認知症の対策には脳トレや多様性のある食事、脳への栄養補給などを併せて行うといいでしょう。
| ■ てんかんがある犬の認知症対策におすすめの栄養成分
・ポリフェノール(アントシアニン、グネチンCなど) |
これらの成分は十分な量を食事から取り入れることは難しいため、サプリメントで効率よく補ってあげることをおすすめします。
さまざまな認知症対策サプリが販売されていますが、動物病院でも取扱いがあるようなエビデンスがある、しっかりとしたサプリメントを選ぶようにしましょう。
犬の認知症については、以下の記事を参考にしてみてくださいね⇩
| 動物介護士が解説|犬の認知症の症状は?予防や対策方法 |
| 動物介護士が解説|犬の認知症を治すことはできる?治療法やできるサポート |
まとめ

犬のてんかん発作は、1回限りでその後発作が起きないこともあれば、繰り返し発作を起こすこともあります。
てんかん発作が続くことで脳にダメージを与える可能性が高まり、認知機能障害や脳機能障害などの後遺症が残ったり、命に関わることもあるため、できる限り発作を起こさないように薬でコントロールすることが重要です。
てんかん発作が起きるとパニックになりがちですが、焦らず冷静に対処して、獣医師と連携しながら上手に付き合っていきましょう。
\ てんかんや認知症ケアにおすすめ! /
老化や脳ケア、シニア犬のからだ全体の健康維持に役立つ動物病院専用サプリメント「トライザ」の無料お試しサンプルは ↓ から
執筆者:高田(動物介護士)