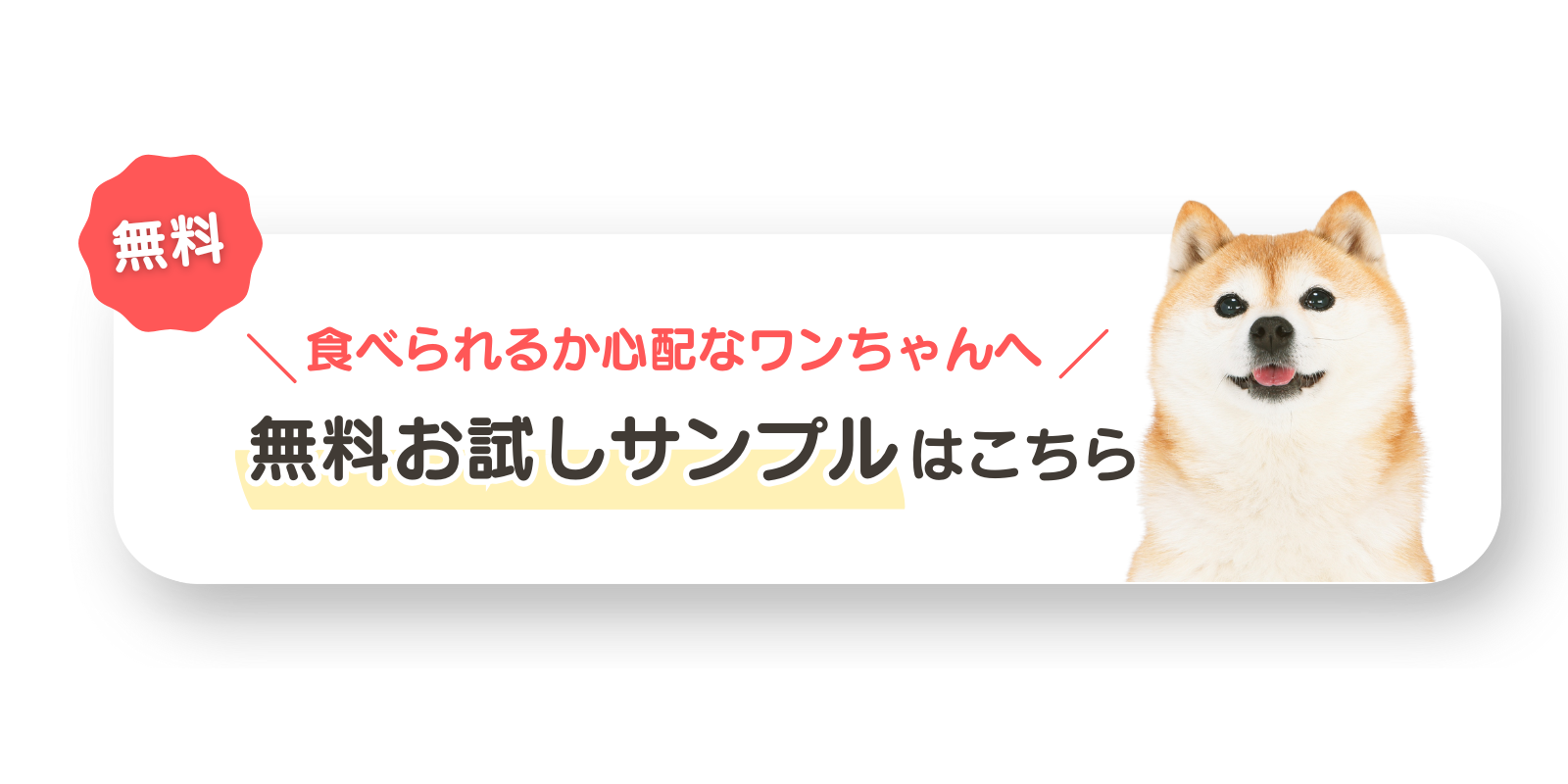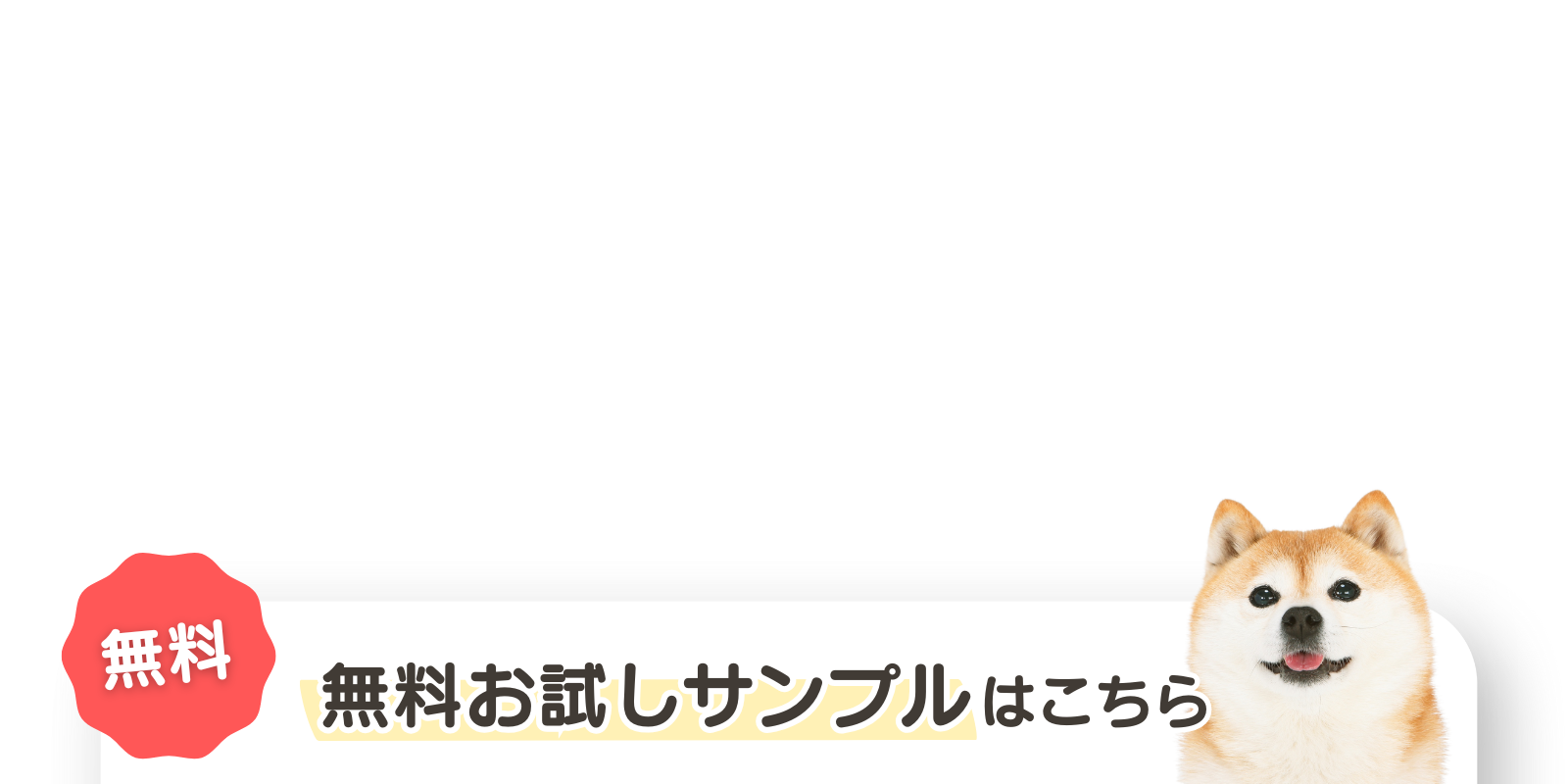犬の歯が抜けるのはなぜ?理由や対処法、歯がないリスクを動物介護士が解説

愛犬の歯が抜けて落ちていたり、おもちゃに血がついている、なんて経験をした飼い主さんもいるのではないでしょうか。
犬の歯が抜けることは、問題のないこともあれば、動物病院で治療が必要なこともあり、歯が抜ける理由を知っておくことが大切です。
今回は、歯が抜ける主な原因や対策、歯がないリスクについてわかりやすく解説します。
| 【執筆者保有資格】
動物介護士、ペットフーディスト、犬の管理栄養士 他 |
そもそも犬の歯は何本あるの?子犬と成犬では違う
犬の歯は、成長段階によって本数が異なります。
子犬は生後3〜4週間頃から乳歯が生え始めますが、生後6〜8週頃には28本の乳歯が揃います。
このとき、犬歯、切歯、前臼歯はありますが、前臼歯の奥にある噛み砕いたりする役割のある後臼歯は存在しません。
その後、生後4〜6か月をかけて永久歯に生え変わり、成犬になると42本の永久歯が揃います。
【子犬・成犬・老犬別】犬の歯が抜ける主な原因

犬の歯が抜ける時に考えられる原因は、ライフステージによって異なります。
それぞれ気をつけてあげることも異なるため、子犬・成犬・老犬に分けて見ていきましょう。
子犬の歯が抜けるのは永久歯への生え変わり
生後数ヶ月の子犬の歯が抜けるのは、乳歯から永久歯への正常な生え変わりによるものです。
個体差もありますが、生後6ヶ月頃には乳歯はすべて抜け落ち、永久歯だけになります。
ただし、犬によっては乳歯が抜けずに残ったまま永久歯が生えてしまう「乳歯遺残」になることもあり、この場合は歯並びや噛み合わせに影響するため、動物病院でのチェックが必要です。
成犬の歯が抜けるのは病気やケガの可能性
成犬の歯が抜けるのは異常なことで、病気やケガの可能性があります。
成犬の80〜90%が歯周病にかかっているとも言われており、どんなにきれいに見えても重度の歯周病だったということもあるため、油断はできません。
また、硬い歯磨きガムやおもちゃなどで歯に負荷がかかったり、口の中をケガしてしまうことで、歯が折れたり抜けるということもあります。
老犬の歯が抜けるのは重度の歯周病の可能性
老犬の歯が抜けるのは、歯への負荷やケガなどを除くと、全身疾患や重度の歯周病の可能性が高いです。
歯周病は全身の健康に影響を及ぼす怖い病気で、心臓病や腎臓病、認知症、誤嚥性肺炎などを引き起こしたり、悪化させることがあります。
なお、老化現象で歯が抜けるのは自然なことと思われがちですが、加齢だけが原因で歯が抜けることはないので注意しましょう。
犬の歯が抜けたときの対処法
では、犬の歯が抜けたときはどうしたら良いのでしょうか。対処法について見ていきましょう。
動物病院を受診する
成犬や老犬の歯が抜けた、またはグラグラしているのを見つけたら、まずは動物病院を受診しましょう。
歯周病やその他の疾患、ケガなどが原因であれば、適切な治療が必要です。
口腔内の状態によってはほかの歯も抜けるリスクがあるため、早めの対処が大切です。
口腔ケアを見直す
犬の残っている歯を守るためにも、口腔ケアを見直しましょう。
理想は毎日の歯磨きと、1年に1回の全身麻酔下での歯石取りです。
無麻酔での歯石取りは、犬の負担の割に思うような結果が得られない場合も多くあります。
また、歯の表面に傷が付きやすく、逆に歯石が付着しやすくなってしまうこともあります。
歯ブラシが難しい場合は、歯磨きシートやガーゼを使用したり、口腔ケア用のサプリメントでサポートするなど、愛犬に合った方法を取り入れましょう。
食事内容を見直してあげる
基本的に犬は丸呑みする習性があるので、歯が抜けても特に問題なく食べることができます。
ただ、喉に詰まらせないように小粒のドライフードにしてあげたり、ふやかしてあげたり、ウェットフードにしてあげるなど、愛犬が食べやすい食事に見直してあげることは大切です。
おもちゃを変更してあげる
硬すぎるおもちゃを与えている場合、柔らかいおもちゃに変更してあげましょう。
「噛む」という行動はとても大切なことなので、噛みやすく安全なおもちゃを選んであげると良いでしょう。
犬の歯が抜けることで起こるリスクも知っておこう

犬は、歯が抜けてもその状態に順応できるため、飼い主さんもあまり深く考えることはないかもしれません。
しかし、歯が抜けることでリスクもあるため、理解しておくことが大切です。
栄養状態が悪化しやすい
犬の歯が抜けると、噛みにくさや痛みによって食事量が減り、体重減少や栄養不足を招くことがあります。
特に高齢犬や持病のある犬では、思うように食事が摂れなくなることで免疫力の低下にもつながるため注意が必要です。
認知症のリスクが高まる
「噛む」という行動は、実は犬にとって重要な脳への刺激源です。
噛むことで脳の血流が促進され、特に学習や記憶をつかさどる前頭前野や海馬を活性化させることがわかっています。
歯が抜けて噛む習慣が減ると、脳への刺激も減少し、認知機能の低下につながる恐れがあります。
犬の認知症については、以下の記事もご覧ください⇩
|
動物介護士が解説|犬の認知症の症状は?予防や対策方法 |
| 動物介護士が解説|犬の認知症を治すことはできる?治療法やできるサポート |
すでに歯が少ない場合は、認知症対策も重要!

現在歯が少ない犬は、脳への刺激が減って認知症のリスクが高まっているという点も見過ごしてはいけません。
ここでは、歯がほとんどない、あるいは全くない犬でもできる脳への刺激やケアの工夫をご紹介します。
食事を「楽しい時間」にしてあげる
ごはんを単なる栄養補給の時間ではなく、コミュニケーションの機会として活用しましょう。
名前を呼びながら食べさせたり、手から与えるだけでも、刺激となって脳を活性化できます。
嗅覚をしっかり使ってもらう
犬は、嗅覚を通じて多くの刺激を受けます。
ご飯のにおいをじっくり嗅がせたり、タオルの中におやつを隠して探してもらうなど、におい探しゲーム(ノーズワーク)を取り入れてみるのがおすすめです。
食感や与え方を工夫して感覚を刺激してあげる
食事は完全なペースト状ではなく、歯ぐきで押しつぶせるくらいの食感を残すことで、より多くの感覚を刺激してあげることができます。
また、まったく歯がなくても、舌で舐めたり、くわえたりすることで口腔内の感覚を刺激できます。
たとえば、ペースト状のおやつを指に塗って舐めてもらったり、ウェットフードをスプーンで与えるといった方法も良いでしょう。
サプリメントで脳の健康をサポートしてあげる

認知症のリスクが高まっていることを踏まえて、脳の健康に必要な栄養を効率よく補えるサプリメントで、脳機能をサポートしてあげましょう。
|
■ 脳の健康維持におすすめの成分 |
脳の健康をサポートするサプリメントはさまざまなものが販売されており、どれを選んだら良いのかわからないという飼い主さんもいるでしょう。
実際に私自身も愛犬にいろいろ試してみましたが、動物病院での取扱いがあるようなエビデンスがある製品のほうが効果を実感しやすく、おすすめです。
犬の歯が抜けることでよくあるQ&A

ここでは、犬の歯が抜けたときによく見られる疑問について、Q&A形式でお答えします。
Q1.愛犬が抜けた歯を飲み込んじゃったけど大丈夫?
A.基本的には、数日後に便と一緒に出てくるので問題ありません。
乳歯などの場合は、中がスカスカの状態なので溶けてなくなってしまうこともあります。
Q2.犬の歯を全部抜いても大丈夫?
A.犬は咀嚼して食べるという口の構造ではないため、全部抜いてしまっても大きな支障はありません。
むしろ、無理に残しておくことで歯周病を悪化させてしまう場合も考えられます。
歯を抜くときは獣医師が口の中の状態を診て判断するため、獣医師にお任せしましょう。
Q3.歯がなければ歯周病の心配はない?
A.歯周病は歯垢や歯石によって引き起こされるため、すべての歯がなければ歯周病になることはありません。
ただ、口の中に歯周病菌は存在するため、誤嚥性肺炎などのリスクはあります。
歯がなくても、口腔ケアサプリメントなどを活用して口の中の環境を良好に保ってあげることが大切です。
まとめ

子犬の歯が抜けることは歯の生え変わりで自然なことですが、成犬や老犬では病気やケガなどが関わっていることが多くあります。
犬はまったく歯がなくても食事自体に大きな問題はなく、歯周病の状態によっては全抜歯ということも珍しくはありません。
しかし、残っている歯を守ってあげることや、まったく歯がない状態でも脳への刺激を工夫してあげることはとても大切なことです。
私たち人間と同じく、年齢を重ねても自分の歯で食感を楽しむことも、美味しく食べるためのひとつの要素です。
日々のケアや食事などを見直し、愛犬が健やかな毎日を送れるようにサポートしてあげてくださいね。
\ 老化・脳ケアにおすすめ! /
老化や脳ケア、シニア犬のからだ全体の健康維持に役立つ動物病院専用サプリメント「トライザ」の無料お試しサンプルは ↓ から
執筆者:高田(動物介護士)