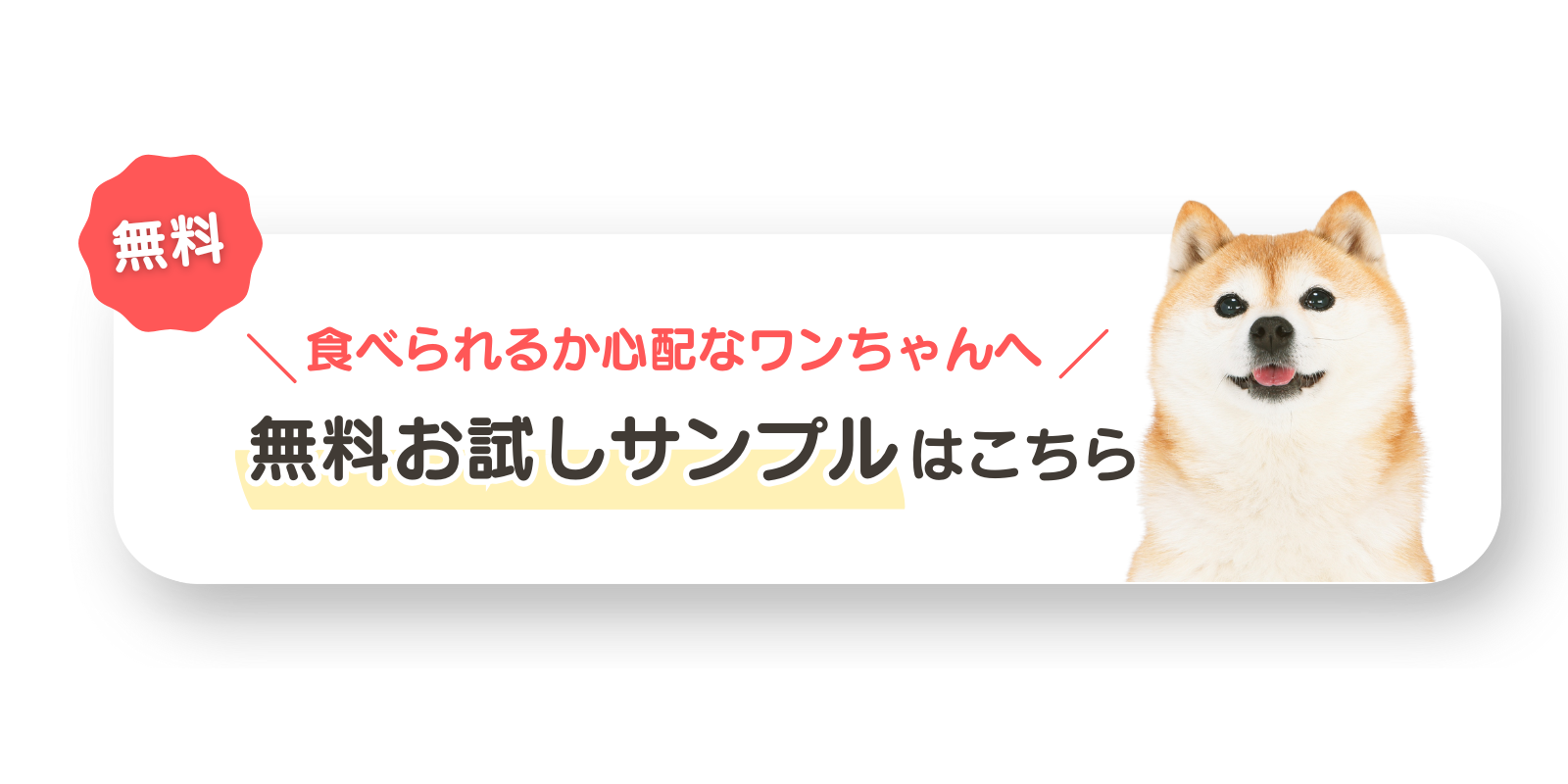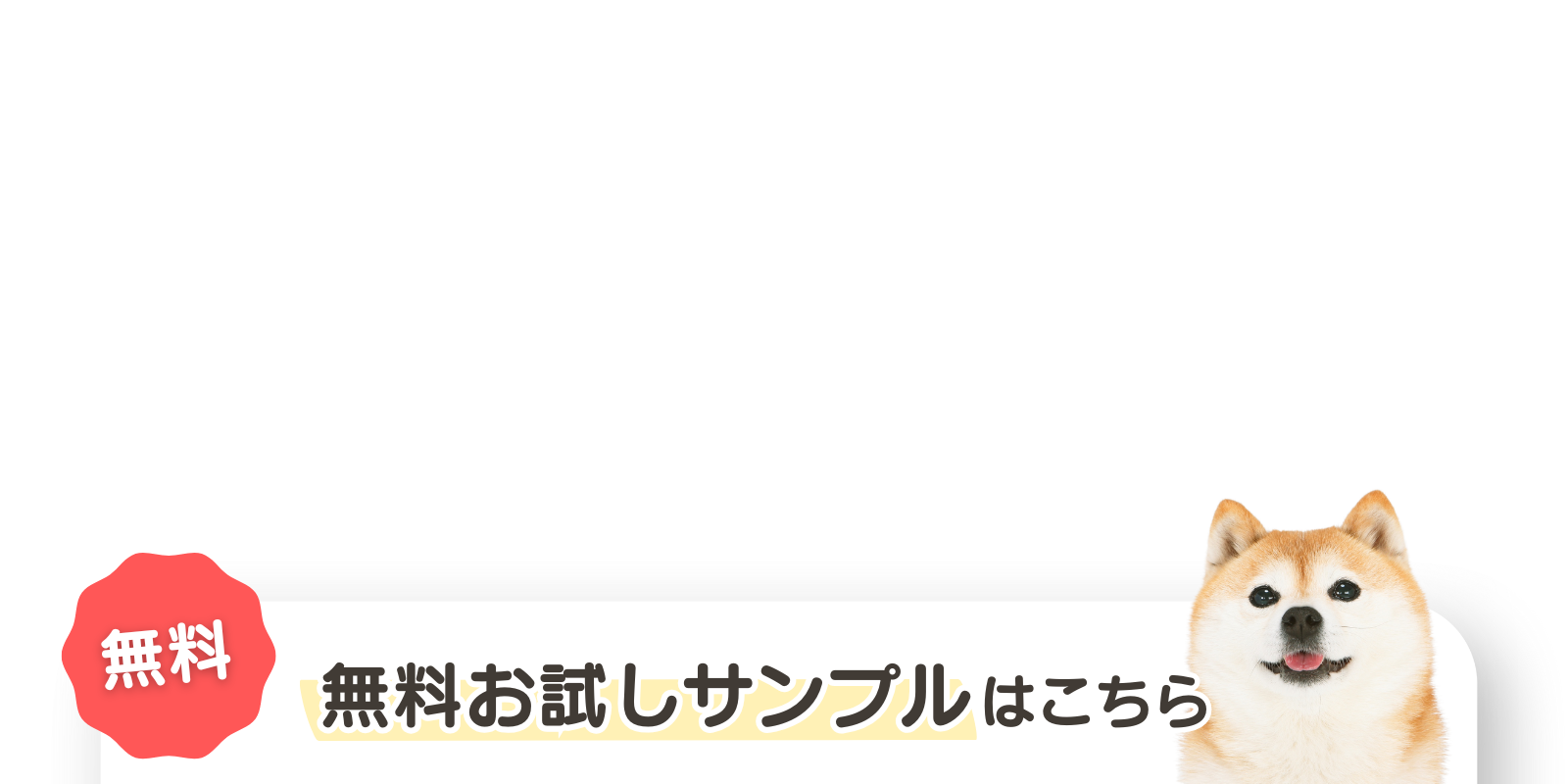老犬になると不安を感じやすくなる!不安なときの行動や和らげる方法

老犬になった愛犬に「不安そうな様子がみられる」と気になっている飼い主さんは少なくありません。
ちょっとした物音に反応したり、飼い主さんの後をずっと付いてきたり、落ち着かずにウロウロするなど、若い頃にはなかった行動に戸惑っているのではないでしょうか。
犬も人間と同じように、年齢を重ねると身体の変化だけでなく、心の変化も起こってきます。
そんな変化のひとつとして見られるのが、「不安を感じやすくなる」ことです。
そこで今回は、高齢の愛犬たちと暮らしていた動物介護士の私が、老犬の不安の理由やみられる行動、対処法について解説します。
| 【執筆者保有資格】
動物介護士、ペットフーディスト、犬の管理栄養士 他 |
老犬が不安を感じやすくなるのはなぜ?
老犬になると不安を感じやすくなりますが、それにはさまざまな理由があります。
若い頃には平気だったことにも敏感に反応してしまうのは、以下のような理由が関係しているのかもしれません。
| ■ 老犬が不安を感じやすくなる主な理由4つ
① 視力・聴力が低下するから |
理由によっては動物病院の受診が必要なこともあるため、なぜ老犬が不安を感じやすくなるのかを理解しておくことが大切です。
① 視力・聴力が低下するから
老犬が不安を感じやすくなるのは、加齢によって視力や聴力が低下するからです。
視力や聴力が低下すると、若いころのように周囲を正確に認識することが難しくなります。
見えにくい、聞こえにくい状態が続くことで不安や混乱を感じやすくなり、警戒心から不安な行動を起こすことがあります。
② 脳が老化するから
老犬になると脳の働きも徐々に低下し、反応が遅くなったり記憶力が落ちたりするだけでなく「安心・不安」といった感情のコントロールも難しくなります。
人間でも、年を重ねるごとに頑固になったり不安感が強くなったりしますが、犬にも同じことが起こるのです。
脳の老化は自然な現象ですが、不安を感じる境界ラインが下がってしまうため、ちょっとした刺激でも強い不安につながることがあります。
③ ストレスに対する感受性が高くなるから
老犬は、加齢による心身機能の低下やストレスホルモンの「コルチゾール」の増加などの影響でストレスを感じやすくなります。
ストレスは脳内の神経伝達物質のバランスを崩し、感情や不安を司る脳の部位を過剰に働かせてしまいます。
その結果、不安が引き起こされやすくなり、不安行動として現れるのです。
④ 認知症による影響から
老犬の不安は、認知症の影響ということも考えられます。
認知症になると、よく知ってる場所やよく知っている人でも分からなくなることがあり、強い不安や恐怖を覚えます。
また、昼夜の区別がつきにくくなったり、目的のない徘徊や夜鳴きが増えるなど、行動面でもさまざまな変化がみられるのも特徴です。
こうした混乱や不安が積み重なることで、ますます落ち着きを失い、不安行動が悪化することも少なくありません。
犬の認知症については、以下の記事で詳しく解説しています⇩
|
動物介護士が解説|犬の認知症の症状は?予防や対策方法 |
|
動物介護士が解説|犬の認知症を治すことはできる?治療法やできるサポート |
老犬が不安なときの行動は?

不安を感じている老犬は、その気持ちを行動で表そうとしますが、飼い主さんが気づきにくいこともあります。
犬は言葉で訴えることができないため、そのサインを見逃さないように、老犬が不安なときにみられる行動を知っておきましょう。
飼い主さんから離れようとしない
老犬が不安を感じると、飼い主さんのそばにずっといたがるようになります。
キッチンまでついてきたり、トイレの前で待っていたりと、ひとりになることを強く嫌がる行動が目立つでしょう。
実際、私の高齢の愛犬(享年18歳)はお風呂場の前で私がお風呂から出るのをずっと待っていたり、トイレの中まで入ってきたりと、常にベッタリでした。
ただ、これらの行動は分離不安でもみられることがあるため、見極めには注意が必要です。
夜鳴きや徘徊をする
夜中に吠えたり、目的もなくウロウロと歩き回ったりするのは、不安を感じている老犬によく見られる行動です。
暗くなってよく見えないという不安や、身体の違和感による不安、認知症の影響などさまざまなことが考えられます。
ただし、急に夜鳴きや徘徊をするようになった場合は、大きな病気が原因となっていることもあるので、早めに動物病院を受診することをおすすめします。
夜鳴きや徘徊については、以下の記事もチェックしてみてくださいね⇩
| 夜泣き=認知症?|老犬の夜泣きの種類と対処法 |
身体を舐め続けたり噛んだりする
不安な気持ちを紛らわせようと、自分の身体の一部を執拗に舐めたり噛んだりする行動がみられることもあります。
同じ場所をずっと舐め続けていると皮膚トラブルを引き起こすこともあり、あまりにも長時間舐めているような場合は対策が必要です。
震えたり呼吸が荒くなる
雷や来客など、ちょっとした刺激に対して過剰に反応し、震えたり息が荒くなるのも不安のサインです。
高齢になると感情をうまくコントロールできなくなり、不安に対する反応が強く出てしまうことがあります。
ただし、体調が悪くて震えたり息が荒くなることもあるので、状況を見極めてあげることが大切です。
老犬の不安を和らげる方法は?

老犬の不安を和らげてあげるには、生活環境を整えたり、日々の接し方に配慮が必要です。
難しいことではなく、少しの工夫で愛犬の気持ちが落ち着いたり安心して過ごせるようになるので、ぜひ実践してみてくださいね。
できる限り環境を変えない
老犬はストレスや不安を感じやすくなるため、できる限り環境を変えないようにすることが大切です。
家具の配置や寝床の場所、トイレの場所などを変えるのは避けたほうが良いでしょう。
また、生活リズムもなるべく一定に保ち、老犬の心身のストレスを最小限に抑えるように配慮してあげてくださいね。
スキンシップと声かけを意識する
飼い主さんが優しく撫でてあげたり、名前を呼んで安心させてあげることで、老犬の不安は和らぎます。
もし別の部屋でひとりで寝かせているのであれば、飼い主さんと同じ部屋で寝かせてあげるといいでしょう。
飼い主さんの存在をそばで感じられると老犬も安心しやすいですし、飼い主さんも急な体調不良などの異変に気づきやすくなります。
【関連記事】
|
犬の幸せとは?老犬の飼い主さんに知っておいてほしい「老犬の十戒」をご紹介 |
|
老犬が喜ぶことは?老犬との過ごし方を動物介護士が解説! |
動物病院を受診する
老犬は不安を感じやすいですが、必ずしも加齢による不安とは限りません。
不安な様子が続く場合や、夜鳴き・徘徊がみられる場合、きっかけもないのに震えたり呼吸が荒くなる場合は大きな病気が隠れていることもあります。
少しでも気になる行動がみられたときは、早めに動物病院を受診することが大切です。
老犬の不安は脳ケアサプリメントを取り入れることも考えよう
不安行動がみられる老犬には、感情をつかさどる脳に必要な栄養を補うための脳ケアサプリメントを取り入れることも検討してみましょう。
近年は、脳の健康維持に役立つ成分を配合したサプリメントがたくさん販売されています。
| ■ 脳の健康維持におすすめの成分 ・ポリフェノール(アントシアニン、グネチンCなど) ・神経栄養因子様化合物(バングレン) ・カロテノイド(アスタキサンチン、ルテイン、β‐カロテンなど) ・DHA ・ビタミンA、C、E など |
実際に私も、年を取るごとに不安が強くなり我慢ができなくなった愛犬に、グネチンCとバングレンが配合された脳ケアサプリメントを与えていました。
愛犬の体質に合っていたようで、落ち着いて過ごす時間が増え、毎日をゆったりと過ごしてくれていましたよ。
どのサプリメントが良いかは老犬の体質によって異なりますが、動物病院でも取扱いがあるエビデンスのあるものを選ぶことをおすすめします。
まとめ

老犬は、身体のさまざまな機能の衰えから不安を感じやすくなるのは自然なことです。
老化は避けられない変化ですが、飼い主さんの関わり方次第で、心が穏やかに保たれることもあります。
少しでも不安を和らげてあげられるように、日々の暮らしの中で優しく寄り添っていきましょう。
飼い主さんの存在が、愛犬にとって一番の安心になります。
これからも穏やかな時間を一緒に過ごしてあげてくださいね。
\ 不安を感じやすくなった愛犬におすすめ /
老化や脳ケア、シニア犬のからだ全体の健康維持に役立つ動物病院専用サプリメント「トライザ」の無料お試しサンプルは ↓ から
執筆者:高田(動物介護士)